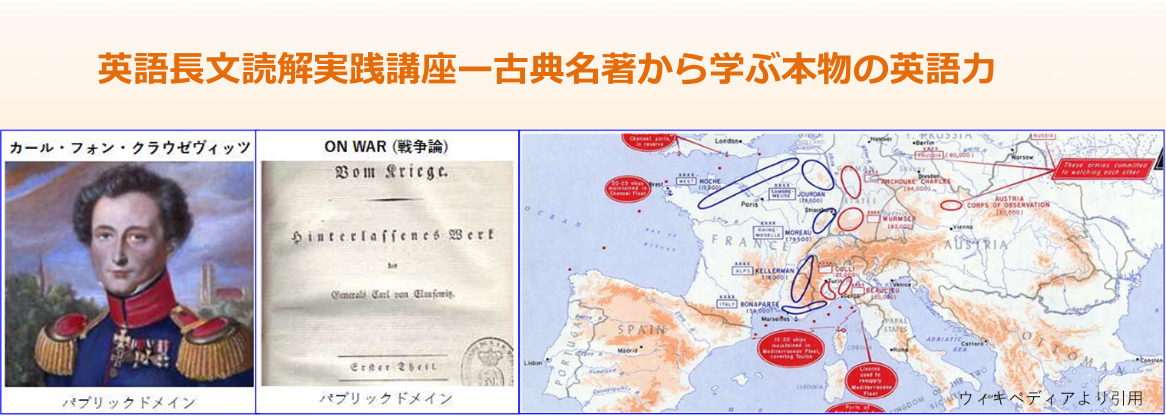Critical Analysis 1. 原文
The influence of theoretical truths on practical life is always exerted more through critical analysis than through doctrine. Critical analysis being the application of theoretical truths to actual events, it not only reduces the gap between the two but also accustoms the mind to these truths through their repeated application. We have established a criterion for theory, and must now establish one for critical analysis as well.
We distinguish between the critical approach and the plain narrative of a historical event, which merely arranges facts one after another, and at most touches on their immediate causal links. These different intellectual activities may be contained in the critical approach.
First, the discovery and interpretation of equivocal facts. This is historical research proper, and has nothing in common with theory.
Second, the tracing of effects back to their causes. This is critical analysis proper. It is essential for theory; for whatever in theory is to be defined, supported, or simply described by reference to experience can only be dealt with in this manner.
Third, the investigation and evaluation of means employed. This last is criticism proper, involving praise and censure. Here theory serves history, or rather the lessons to be drawn from history.
In the last two activities which are the truly critical parts of historical inquiry, it is vital to analyze everything down to its basic elements, to incontrovertible truth. One must not stop half-way, as is so often done, at some arbitrary assumption and hypothesis. The deduction of effect from cause is often blocked by some insuperable extrinsic obstacles: the true causes may be quite unknown. Nowhere in life is this so common as in war, where the facts are seldom fully known and the underlying motives even less so. They may be intentionally concealed by those in command, or, if they happen to be transitory and accidental, history may not have recorded them at all. That is why critical narrative must go hand in hand with historical research. Even so, the disparity between cause and effect may be such that the critic is not justified in considering the effects as inevitable results of known causes. This is bound to produce gaps ? historical results that yield no useful lesson.
All a theory demands is that investigation should be resolutely carried on till such a gap is reached. At that point, judgment has to be suspended. Serious trouble arises only when known facts are forcibly stretched to explain effects; for this confers on these facts spurious importance.
第1パラグラフ
※語・句注釈
*① exert (動詞) = 「使う、働かせる、及ぼす、全力で努力する」 *① doctrine (名詞) = 「主義、教養、学説、理論」 *② critical analysis (名詞句) = 「批判分析、批判的分析」 *③ as well (副詞・tooと同じ意味) = 「その上、更に」 *④ distinguish (動詞) = 「区別する」他動詞: distinguish A from B(, 自動詞: distinguish between A and B(AとBの相違を見分ける) 等. *④ at most (前置詞句→副詞句) = 「せいぜい」 *④ causal (形容詞) = 「因果関係のある、原因となる」 *④ immediate (形容詞) = 「直近の、目の前の、目近の」 *⑩ by reference to experience (前置詞句) = 「経験に照らして、経験を参照して」 *⑫ praise and censure (名詞句) = 「毀誉褒貶(きよほうへん)=褒めたり貶したりすること」
第2パラグラフ
※語・句注釈
*① inquiry (名詞) = 「研究・調査・探求」 *① incontrovertible (形容詞) = 「議論の用地の無い、明らかな」⇔ controvertible *③ insuperable (形容詞) = 「打ち勝つことの出来ない、克服する事が出来ない」 *⑤ transitory (形容詞) =「一時的な、儚い、つかの間の」 *⑦ disparity (名詞) = 「差異・不均衡・格差」 *⑦ inevitable (形容詞) = 「避けられない、不可避の、いつもの、お定まりの」 *⑧ S is bound to・・(成句的表現) = 「~することになっている、~する運命にある、当然のごとく~することになる」 *⑪ confer (動詞) = 「与える、授ける」 *⑪ spurious (形容詞) = 「にせの、いい加減な、偽造の」
Critical Analysis 1. 解説
第1パラグラフ
① The influence of theoretical truths on practical life is always exerted more through critical analysis than through doctrine. ② Critical analysis being the application of theoretical truths to actual events, it not only reduces the gap between the two but also accustoms the mind to these truths through their repeated application. ③ We have established a criterion for theory, and must now establish one for critical analysis as well.
④ We distinguish between the critical approach and the plain narrative of a historical event, which merely arranges facts one after another, and at most touches on their immediate causal links. ⑤ These different intellectual activities may be contained in the critical approach.
⑥ First, the discovery and interpretation of equivocal facts. ⑦ This is historical research proper, and has nothing in common with theory.
⑧ Second, the tracing of effects back to their causes. ⑨ This is critical analysis proper. ⑩ It is essential for theory; for whatever in theory is to be defined, supported, or simply described by reference to experience can only be dealt with in this manner.
⑪ Third, the investigation and evaluation of means employed. ⑫ This last is criticism proper, involving praise and censure. ⑬ Here theory serves history, or rather the lessons to be drawn from history.
☆① 主語(主部)は The influence of theoretical truths on practical life、名詞 + 前置詞 + 名詞 + 前置詞 + 名詞の名詞句で、文自体は、所謂、典型的な名詞構文の1つである. この部分を直訳すると「実生活上の理論的真理の影響」と、助詞「の」を伴う名詞の羅列になり、日本語らしくない肩の凝った表現になる. 名詞 + 前置詞 + 名詞 + 前置詞が続く名詞構文の場合は、そのまま訳すとすんなり意味を取ることが難しい. このような場合、動的表現を持つ単語が名詞化されていることも多く、当文では influence がそれに充たる. 名詞の influence を動詞として、Theoretical truths influence practical life と表す事が理解出来ると、influence を動的に捉えて、「理論的真理が実生活に影響をおよぼす」ことを述べているので、もう一歩踏み込んで「理論的真理が実生活に影響するのは」或は「理論的真理が実生活に影響を及ぼすのは」という理解に繋がってくるだろう. つまり、名詞 + 前置詞 + 名詞 + 前置詞 + 名詞の表現では、動的表現で表せる場合には、名詞を動詞化して訳すと、日本語らしさが出て来る.前置詞 of は、A of B の形で「B の A」と日本語では「~の」に充たる場合が殆どで、代表的な働きとして帰属 (a member of the group 等)・所有 (a friend of mine 等) を表す. 一方で、the influence of theoretical truths ように、動詞の名詞化表現で「理論的真理が~に影響を及ぼす」という主格関係を表したり、the discovery of a new continent 「新大陸を発見すること」のように、目的格関係を表す場合もあるので、名詞 + 前置詞 + 名詞 + 前置詞 + 名詞の表現には、前後脈絡と併せて、その解釈に注意が必要となる.
☆② Critical analysis being the application of theoretical truths to actual events, it not only reduces the gap between the two but also accustoms the mind to these truths through their repeated application. 当文の理解、少々迷うのではないだろうか. 1節目の Critical analysis being the application…、そして2節目の it から始まる節、これをどう理解するか. 分詞構文を習ったことのある人は、名詞 critical analysis の直後にある現在分詞の being に着目して、何かしらピンと来たひともいるかも知れない. 先ず、思い付くのは、独立分詞構文で、主節の主語と分詞構文(従属節)の主語が異なる場合には、分詞構文 (従属節) の主語は分詞の前に置くという規則だろう. 読んでいくうちに、これも独立分詞構文で主節の主語 it と分詞構文 (従属節) の主語である critical analysis が異なるのかと思いきや、文脈から考えると論理的には、critical analysis も主節である it も critical analysis と同義でなければ全く当文は意味をなさなくなることが解って来る. そうなると、当分詞構文は、これまで我々が学校教育で教わってきた、①通常の分詞構文(主節の主語と分詞構文の主語が同じ場合は分詞構文の主語は省く)、②独立分詞構文(主節の主語と分詞構文の主語が異なる時は、分詞構文の意味上の主語は分詞の前に置いておく)、③懸垂構文(分詞構文=従属節の主語が主節の主語とは異なるのに、分詞構文の主語が省略されている=学校文法では非文法とされているものの実際の英文資料などではよく目にするものである)、④分詞構文の慣用的表現には当て嵌まらない分詞構文である事が解る. 戦争論の原文はドイツ語で書かれ、その後英文に翻訳されたわけだが、ここでは英語版表記に従い、この通りのままで理解するように努める. しかし、日本で教わる学校英文法ではどうしても整合性を以てして説明し切れない表現にも遭遇する事もあるので、そこは色々な経験・知識・想像力を駆使して読解を行う必要がある. と同時に、学校で習う文法事項は土台となるものであるが、それが全てと思い込んではならないという事、いろいろなところで例外というものも存在するものだ、という認識は持っておきたい. 総合的に考えて見 て(ある意味、All things considered,) この文は、Being the application of theoretical truths to actual events, critical analysis not only reduces the gap between the two but also accustoms the mind to these truths through their repeated application. と表現された方が英文法の説明がし易い文になると考えられ得ないだろうか、との提言に留めておきたいと思う.
☆④ ここでの distinguish は自動詞の働きで distinguish between ① the critical approach (of a historical event) and ② the plain narrative of a historical event で「① 批判的アプローチ(手法)と② 歴史の単なる語りとの区別」を表す. コンマ + which + merely + arranges・・・ は直前の先行詞 the plain narrative of a historical event に対する追加情報を補足している非制限用法(継続用法)の関係代名詞としての働き. 先行詞がthe plain narrative of a historical event の為、arranges と三単現のsがついている. ここで非制限用用法を使って言わんとしていることは、the plain narrative of the historical event というものは、「,which merely arranges facts one after another, and at most touches on their immediate causal links」であってそれ以外のものはない、という事である. もし、これが the plain narrative of the 」historical event which arranges・・・・となっているとすれば、「the plain narrative of the historical event には他にも解釈の意味があるが、この文脈での the plain narrative of the historical event は merely arranges facts one after another, and at most touches on their immediate causal links である」という事を意味することになり、これが制限用法と非制限用法の違いである. この区別は非常に重要なので押さえておきたい. つまり、1つしかなく特定する必要のないものを制限用法で表すべきではない、ということである.
☆ ⑦ This is historical research proper. proper は、a proper way (適切な方法)、the proper person for the job (その仕事に相応しい人) など普通の形容詞と同じ名詞の前に置かれる使い方がある一方で、 literature proper (純文学) や当文のように historical research proper (本来の歴史研究) のように名詞の後に置かれる後置修飾形容詞としての使い方もある. この場合、proper の訳し方としては、「厳密な意味においては、本来の」の意味を直前の名詞につけて訳すと良い.
☆ ⑩ It is essential for theory; for whatever in theory is to be defined, supported, or simply described by reference to experience can only be dealt with in this manner. ポイントは2つ. 1つ目は、;(セミコロン) の後の for は前置詞でなく、理由を表す接続詞としての用法であることを確認. 2つ目は、複合関係代名詞 whatever である. これは文字通り what に ever が付いたもので、what も whatever も先行詞を含む関係代名詞であるが、what は the thing that・・・ に、whatever は anything that・・・ に書き換えられる. whatever は what の強調形と説明される場合があるが、強調という一言で説明されてもどう解釈すればよいかが書かれておらず、それだけではなかなか実用の域を出ないので、以下のように考えて良いだろう. つまり、whatever は anything that・・・で書き換えられるように、what で示されるものの制限が取り払われた一層大きな枠組みを内包している、と. 当文では、whatever で導かれる名詞節 (下線部) がかたまりとなって、文の主語になっているのである.複合関係代名詞 whatever についての例文を以下に挙げる.Ex.1. I will do what I can. = I will do the thing that I can.Ex.2. I will do whatever I can. = I will do anything that I can.what も whatever も名詞節を導くので主語・補語・目的語になり得る. Ex.3. Whatever is to be done, can only be done adequately by the help of certain zest.上文の主語は、先行詞をその中に含む複合関係代名詞 whatever に導かれる Whatever is to be done で、訳は「しなくてはならないものは全て、熱意という助けがあって初めて十分に遂行され得る.」となる.☆ ⑪ Third, the investigation and evaluation of means employed. 当文は、日本語で言う箇条書きの形. 末尾のemployed は過去分詞の形容詞用法で後置修飾語となって前の名詞means (手段) に掛かる.
☆ ⑫ This last is criticism proper, involving praise and censure. 文末の proper は⑦文目と同じ用法. involving・・・以下は、分詞構文.
第2パラグラフ
① In the last two activities which are the truly critical parts of historical inquiry, it is vital to analyze everything down to its basic elements, to incontrovertible truth. ② One must not stop halfway, as is so often done, at some arbitrary assumption and hypothesis. ③ The deduction of effect from cause is often blocked by some insuperable extrinsic obstacles: the true causes may be quite unknown. ④ Nowhere in life is this so common as in war, where the facts are seldom fully known and the underlying motives even less so. ⑤ They may be intentionally concealed by those in command, or, if they happen to be transitory and accidental, history may not have recorded them at all. ⑥ That is why critical narrative must go hand in hand with historical research. ⑦ Even so, the disparity between cause and effect may be such that the critic is not justified in considering the effects as inevitable results of known causes. ⑧ This is bound to produce gaps ? historical results that yield no useful lesson.
⑨ All a theory demands is that investigation should be resolutely carried on till such a gap is reached. ⑩ At that point, judgment has to be suspended. ⑪ Serious trouble arises only when known facts are forcibly stretched to explain effects; for this confers on these facts spurious importance.
☆ ② as is often so done の as は疑似関係代名詞としての使用で、主節全体 (One must・・・at some arbitrary assumptions and hypothesis.) が先行詞. One must not stop halfway at some arbitrary assumption and hypothesis, as is so often done. と as 節を文末に持って来ることも可能. 文末が as 節ではなく、, which で始まれば、非制限用法の関係代名詞節になることも要確認. 当文では、as is so often done はその位置から挿入節のような形になっている.
☆ ④ Nowhere in life is this so common as in war, where the facts are seldom fully known and the underlying motives even less so. 当文は、否定の副詞表現が文頭に出ることによる否定語と原級比較 (so・・A as ~ B或は as・・A as ~ B) の組合せはで、入試では定番の頻出問題である. 否定語と原級比較を併用することで実質上の最上級表現になっている. so common の個所では、so が副詞で 形容詞の common を修飾している. 否定語と原級比較による最上級表現は勿論重要であるが、同じく重要なのは、当文は、否定語(否定の副詞・句・節)を文頭に置く事で倒置表現が表される、文頭の副詞(副詞句・副詞節)による強制倒置がおこなわれている、ということである.
☆ ⑥ That is why critical narrative must usually go hand in hand with historical research. 当文のThat is whyは、ある種、成句的表現で前文の内容を受ける形で、and so に相当し「そういう訳で、それ故、そういう理由で」を表すと覚えておく方が良い. 1語の同義語としては、therefore や hence などがある. 但し、文法的説明となると、関係副詞の用法で先行詞が省略された形であると、考えるのが一般的である. 当文を、That is the reason why critical narrative must usually go hand in hand with historical research. とすれば、the reason は先行詞となり、why が関係副詞の働きで why 以下は形容詞節となって (後置修飾となって)先行詞の the reason を修飾することになる. 但し、当文は、the reason がない、That is why critical narrative must usually go hand in hand with historical research. なので、why 以下の節は形容詞節ではなく、先行詞が省略されたものと考え、why は先行詞の the reason を含んだものとして理解し、why 節以下は名詞節と解釈する. 文法的にはこれが正しい説明となることは要確認.※先行詞を含んだ why の例文Ex.1: Why he went to the UK is unknown. 「何故彼がイギリスに行ったのかは知られていない。」若しくは「何故彼がイギリスに行ったのかは分からない。」Ex.2: I want to know why the war broke out. 「私は戦争が起きた理由を知りたい。」
☆ ⑦ Even so, the disparity between cause and effect may be such that the critic is not justified in considering the effects as inevitable results of known causes. such と that の組合せで程度や結果を表す副詞節を作る. the disparity between cause and effect may be such の such は「それほどまでの、そんなにも」の意を表し、「そんなにも」とは「どんなもの」なのかが、that 節以下で説明されている. また、この文は、Such is the disparity between cause and effect that・・・への書き換えも可能で、意味は全く同じである. ☆ ⑪ Serious trouble arises only when known facts are forcibly stretched to explain effects; for this confers on these facts spurious importance. の for は理由を表す接続詞の用法. this (主語) + confers (V) on these facts (副詞句) supurious importance (O) の関係で、他動詞 confers と 目的語 supurious importance の間に副詞句 on these facts が入っている形.
~重要文法事項~
疑似関係代名詞
as, than, but は本来の機能としては接続詞であるものの、英文中で関係名詞のような働きをすることがある. このような働きをする場合に限って as, than, but は疑似関係代名詞として扱われる.
1. as の場合
先ず、as からみていく. 関係代名詞と同じように、制限用法と非制限用法がある. これは、関係代名詞においても、制限用法と非制限用法とが存在する関係性が見て取られる.
【制限用法】
文中の単語に the same, such, as などがある場合、これらの語と相関的に as が用いられる.
Ex.1: He has the same problem as I (have). 「彼は私と同じ問題を抱えている.」この場合、本来は 節を導くので S + V が必要となり、as I have となるが、英語では同じ言葉が出来る限り省略するので as の後は have を省いて I だけになっている. as は自らが導く節で have の目的語になっている. 先行詞は the same problem.
Ex.2: He is as brave a soldier as ever lived. 「彼は古今稀に見る勇敢な兵士である.」as は as が導く節内で主語の働きをしている.
Ex.3: There is as much money as is needed. 「必要なだけの金はある.」as は as が導く節内で主語の働きをしている.④ I don’t like such a plan as you talked about. 「私は、昨日あなたが話をしていた(話題にしていた)ような計画案は好きではない.」 as は as が導く節内で目的語の働きをしている. such a plan が about の目的語になっている. ちょうど関係代名詞の目的格のような働きである.
【非制限用法】
Ex.1: He is absent today too, as is often the case. 「よくあることだが、彼は今日も欠席している.」 as は主節全体、he is absent too を受けている. He is absent today too, which is often the case. となれば、which は継続用法の関係代名詞で、主節に補足説明を加える形である事に気付くだろう.
Ex.2: As was predicted, he won the race. 「予想された通り、彼がそのレースに勝った。」文頭の as は、主節の he won the race. 全体を受けている.
Ex.3: He is a German, as you may notice from his accent. 「彼はドイツ人だ、君も彼のアクセントから気付いているかも知れないが」 例えば、He is a German, which you may notice from his accent. となれば、コンマ + which は関係代名詞の継続用法になり、結局の意味としては同じであるが、敢えて訳すなら「彼はドイツ人であるが、君も彼のアクセントから気付いているところだが」ことになろう.As you may notice from his accent, he is a German. としても同じことで、as の先行詞は2節目の he is a German 全体である.
Ex.4: As you know, he is from the United States. 「ご存じのように、彼はアメリカ人です.」as は、後ろの節全体、he is from the United States を受けている.
2. .than の場合
Ex.1: There is more money than is needed. 「必要以上の金がある.」例えば、There is more money ( ) is required. とあり、空欄に何が入るかを問うているとしよう. これをどう解くか.先ず、( ) の後が is needed となっているので、空欄には何かしら主語に充たることばが入るだろうとことは想像出来る. しかも、先行詞と考えられる money に掛かる節 (形容詞節 → 関係代名詞節) になるだろう、と考えると、関係代名詞の that 若しくは which であろうかと判断出来るはずである. しかし、1.直前の名詞 more money と比較表現と呼応する必要がある、2. is needed を導く主語の役割が必要とされることを考慮すると than が適切ではないかとも考えられる. この場合は、比較表現であることが優先され ( )内には than が入り、There is more money than is required. 「必要とされる以上の金がある.=必要以上の金はある.」となる. ここでは、than は is required の主語となり、代名詞として働くと同時に、節(形容詞節)を導いて先行詞の money を修飾する関係代名詞の働きをしている. つまり、この than は比較級を含む先行詞 more money の代名詞として機能しており、通常関係代名詞として使われる that や which と区別して疑似関係代名詞と呼ばれている.
3. but の場合
否定の意味を持つ語(準否定語・否定語)が先行詞となり、but で 関係代名詞の that やwho で、 that ~ not 或は who ~ not の形容詞節と同じ形でが先行詞に掛かり(修飾する) 「~しない~はない」の意を表す.
Ex.1: There is no one but makes mistakes. = There is no one who does not make mistakes.「間違いをしない人なんていないよ。」
Ex.2: There was not a man but had a gun in his hand in that battle. = They all had guns in their hands in that battle. 「あの戦いでは、銃を持ってない人間なんて1人もいなかった = 全ての人間が銃を所持していた。」の意.
本章 Critical Analysis 1. 第2パラグラフ②文目 One must not stop halfway, as is so often done, at some arbitrary assumption and hypothesis. に挿入句のように as is so often done とあるが、この as が疑似関係代名詞の用法で、as は One must not stop halfway at some arbitrary assumption and hypothesis の主節全体を先行詞としている. この他にも、他の章でみられるように、as we have seen, などの表現があるが as は seen の目的語となっており、このような場合は全て疑似関係代名詞である.
Critical Analysis 1. 訳文
第1パラグラフ
① 理論的真理が実生活に影響を及ぼすのは、一方的な教えによるよりも批判的分析を通してのものの方が大きい。
② 批判的分析は、理論的真理を現実の出来事に適用するものなので、2つの間の溝を小さくするだけでなく、繰り返し応用することで思考力を理論的真理に 馴染めせるものである。
③ 我々はこれまでに理論についての基準を確立させてきており、今ここでは批判的分析についても基準を確立しなくてはならない。
④ 歴史的史実に対して批判的に取り組むことと、只単に史実を語ることとは区別する必要がある。といのも、後者は、起こった事実を1つ1つ整理して、せいぜいそれらの連続的因果関係の言及に留まるに過ぎないからだ。
⑤ 批判的に歴史に迫る際には、以下3つの種類を異にする知的活動がある。
⑥ 第1は、事実とされていても曖昧さが残るものや疑いのありそうなものを見つけ出すこと。
⑦ これは本来の歴史的研究であり、理論そのものとは何の関係もない。
⑧ 第2は、発生した結果からその原因に迫る活動である.
⑨ これが本来の批判的分析である。
⑩ そして、このことが理論の構築に必須なものとなる。というのも、理論に於いては、経験に依って確定され・支持をされ或いは説明されるべき全てのこと が、この批判的分析によってのみ初めてなされ得るからである。
⑪ 第3は、戦争で使用された手段の調査とその評価である。
⑫ これが本来の批判で、毀誉褒貶に関わってくる。
⑬ ここに於いて、理論は、歴史に役立つものになると言うか、歴史にから得られる教訓としての役割をなすのである。
第2パラグラフ
① 歴史的考察の真に批判的な部分である第2・3の活動では、全ての事柄をその基礎的要素にまで、議論の余地のない真実にまで分析を行う事が必要である。
② よくあることだが、批判的分析では勝手な想定や仮説でもって中途半端に終わるがあってはならない。
③ 原因から結果を導くのは、時として乗り切れそうにもない外的障害により妨げられることがある。つまり、真の原因は殆ど知られることはない、ということである。
④ このことは、人生のどこに於いても、戦争に於いてほど、起こり得るものはない。というのも、戦争では、事実が十分に知らされることは滅多とないし、ましてやその真の動機については尚更のことである。
⑤ 真の原因や動機などは、戦争指揮の立場にある者に依って意図的に隠されるかも知れないし、或はもしそれらがたまたまその場限りのものであれば、歴史 によって全てが明らかにされるものではないだろう。
⑥ だからこそ、批判的に説明を行うには、歴史的研究と連携して行わなければならない。
⑦ しかし、例えそううであるにせよ、批判的な歴史の説明と歴史的研究の間には原因と結果についての大きな食い違いが生まれることのあり、そのような時には、結果が既知の原因の当然の帰結であると見なすことが正しくない場合が出て来る。
⑧ そうすると、必然的に2つの説明と研究の間に裂け目とも言えるものが生まれ、至った歴史的結論は何の教訓にもなり得ないことがあるのである。
⑨ 理論として必要なのは、研究はそのような食い違いが見られるまで徹底的に行われ、そのような場合には、結果についての判断は一旦棚上げとしなくてはならない。
⑩ というのも、既知の事実で以て無理くりに結果を説明しようとするような時に初めて、深刻な問題が発生するからである。何故なら、そうすることで、これらの事実に誤った重要性が与えられてしまうからである。