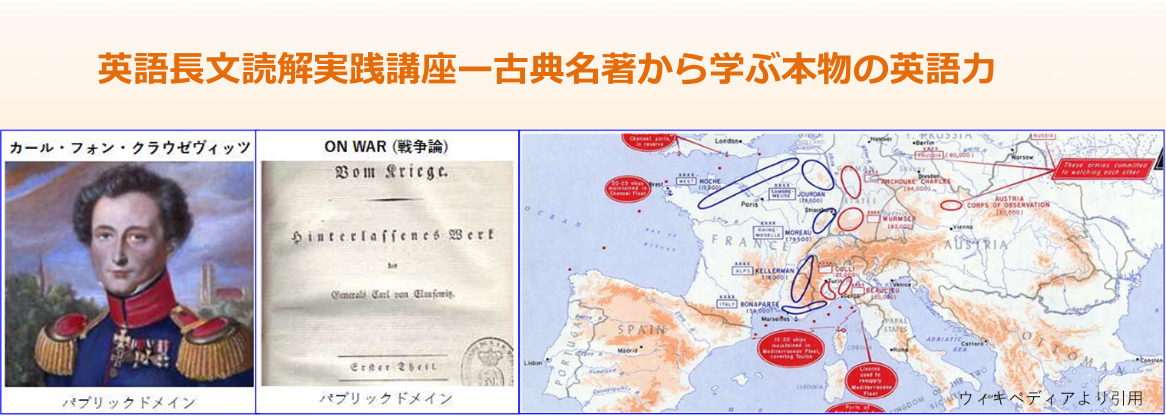Critical Analysis 2. 原文
Apart from that problem, critical research is faced with a serious intrinsic one: effects in war seldom result from a single cause; there are usually several concurrent causes. It is therefore not enough to trace, however honestly and objectively, a sequence of events back to their origin: each identifiable cause still has to be correctly assessed. This leads to a closer analysis of the nature of these causes, and in this way critical investigation gets us into theory proper.
A critical inquiry―the examination of the means―poses the question as to what are the peculiar effects of the means employed, and whether these effects conform to the intension with which they were used. The peculiar effects of the means leads us to an investigation of their nature―in other words, into the realm of theory again.
We have seen that in criticism it is vital to reach the point of incontrovertible truth; we must never stop at an arbitrary assumption that others may not accept, lest different propositions, equally valid perhaps, be advanced against them: leading to an unending argument, reaching no conclusions, and resulting in no lesson.
We have also seen that both investigation of the causes and examination of the means leads to the realm of theory―that is, to the fields of universal truth that cannot be inferred merely from the individual instance under study. If a usable theory does not indeed exist, the inquiry can refer to its conclusions and at that point end the investigation. However, where such theoretical criteria do not exist, analysis must be pressed until the basic elements are reached. If this happens often, it will lead the writer into a labyrinth of detail: he will always have his hands full and find it almost impossible to give each point the attention it demands, as a result, in order to set a limit to his inquiries, he will have to stop short of arbitrary assumptions after all. Even if they would not seem arbitrary to him, they would do to others, because they are neither self-evident nor have they been proved.
In short a working theory is an essential basis for criticism. Without such a theory, it is in general impossible for criticism to reach that point at which it becomes truly instructive―when its arguments are convincing and cannot be refuted.
第1パラグラフ
※語・句注釈
*① apart from ~ (前置詞句) = 「~はさておき、~だけではなく」 *① intrinsic (形容詞) = 「内的な」 *② a sequence of ~ = 「一連の~」 *④ as to (前置詞句) = 「~について」 *⑥ assumption (名詞) = 「想定・推測・思い込み」 *⑥ incontrovertible (形容詞) = 「否定できない・反論出来ない → 明白な」 *⑥ lest (接続詞) = 「SがVするといけないから、~しないように」
第2パラグラフ
※語・句注釈
*① infer (動詞) = 「推測する、推論する」 *① realm (名詞) = 「領域、範囲、王国」 *④ labyrinth = maze (名詞) = 「迷路、迷宮、迷路のように入り混じること」be in a maze 「当惑して」 *⑥ in short (前置詞句) = 「手短に言えば、手短に言うと」 *⑦ refute (動詞) = 「論破・反論する、否定する」
Critical Analysis 2. 解説
第1パラグラフ
① Apart from that problem, critical research is faced with a serious intrinsic one: effects in war seldom result from a single cause; there are usually several concurrent causes. ② It is therefore not enough to trace, however honestly and objectively, a sequence of events back to their origin: each identifiable cause still has to be correctly assessed. ③ This leads to a closer analysis of the nature of these causes, and in this way critical investigation gets us into theory proper.
④ A critical inquiry―the examination of the means―poses the question as to what are the peculiar effects of the means employed, and whether these effects conform to the intention with which they were used. ⑤ The peculiar effects of the means lead us to an investigation of their nature―in other words, into the realm of theory again.
⑥ We have seen that in criticism it is vital to reach the point of incontrovertible truth; we must never stop at an arbitrary assumption that others may not accept, lest different propositions, equally valid perhaps, be advanced against them: leading to an unending argument, reaching no conclusions, and resulting in no lesson.
☆ ① Apart from that problem, critical analysis is faced with a serious intrinsic one: effects in war seldom result from a single cause; there are usually several concurrent causes. 当文での intrinsic は、Critical Analysis ? 1.の第2パラグラフ③文目の by some insuperable extrinsic obstacle の extrinsic「外的」の対語として使用されており、ここでは「内的な、内在する」の意を表す. intrinsic は多く使用される語であり、意味としては「本来備わっている、本質的な」などの意味も含む. be faced with ~A は、「Aに直面している」の意.
☆ ② It is therefore not enough to trace, however honestly and objectively, a sequence of events back to their origin: each identifiable cause still has to be correctly assessed. では、it は形式主語で、真主語は to trace 以下. however honestly and objectively のhowever は honestly and objectively を修飾する副詞としての働きで、1) however + 形容詞の形と、2) however + 副詞の形がある. 当文では、however honestly and objectively で「どんなに誠実にしかも客観的であっても」の譲歩の意を表す. however honestly and objectively (it is / it may be) と主語と動詞が省略された譲歩節と捉えても良い. 特に、主節内に入り込む譲歩節の場合には、この主語と動詞が省略される場合もよくある. 例: Every analyst, however skillful (he is / he may be), must take a promotion exam. 「アナリストは皆、どんなに有能であっても、昇進試験を受けなくてはならない。」
☆ ⑥ We have seen that in criticism it is vital to reach the point of incontrovertible truth; we must never stop at an arbitrary assumption that others may not accept, lest different propositions, equally valid perhaps, be advanced against them: leading to an unending argument, reaching no conclusions, and resulting in no lesson.We have seen that ~ は、「that 節内の事を確認してきた」の意を表す. it is vital to that 節内の、in criticism we must never stop at an arbitrary assumption that others may not accept では、現在の英語の運用では criticism の後にコンマ(,)を打っておいた方が理解し易いだろう. an arbitrary assumption that の that は制限用法の関係代名詞. assumption は 先行詞で、accept の目的語. 確認事項だが、that 節内の in criticism は that 節内で使用されているので、この副詞句は主節の動詞 (have) seen に掛かるのでは無く、節内の動詞である never stop に掛かる. lest は後に節 (S + V: 主語+動詞) を導いて「S が V するといけないから、S が V しないように」と (just) in case や for fear that S + V と同じ意味を示す. lest は文語的表現で仮定法現在が使用されるのが普通だが、should, may や直説法が使われる時もあるが、基本的には文語的表現. :(コロン)以下は、これまで述べて来た内容の纏めとして、「議論が尽くされることはなく、何の結論にも至らないし、教訓を得るなどのことは何も無い」の意を表している. 文法としては、懸垂分詞構文に充たるものである.
第2パラグラフ
① We have also seen that both investigation of the causes and examination of the means lead to the realm of theory―that is, to the fields of universal truth that cannot be inferred merely from the individual instance under study. ② If a usable theory does indeed exist, the inquiry can refer to its conclusions and at that point end the investigation. ③ However, where such theoretical criteria do not exist, analysis must be pressed until the basic elements are reached. ④ If this happens often, it will lead the writer into a labyrinth of detail: he will always have his hands full and find it almost impossible to give each point the attention it demands, as a result, in order to set a limit to his inquiries, he will have to stop short of arbitrary assumptions after all. ⑤ Even if they would not seem arbitrary to him, they would do to others, because they are neither self-evident nor have they been proved.
⑥ In short, a working theory is an essential basis for criticism. ⑦ Without such a theory, it is in general impossible for criticism to reach that point at which it becomes truly instructive―when its arguments are convincing and cannot be refuted.
☆ ① ―that is, to the fields of universal truth that cannot be inferred merely from the individual instance under study. ―(ダッシュ)は、直前の名詞や内容を殊更に強調する為や追加情報を加えたり、具体的に説明したりするときに用いる. ある意味、: (コロン) と同じ働きである. 当文の that は主格の関係代名詞 (制限用法) でtruth を後置修飾している.
☆ ② If a usable theory does indeed exist と、本動詞 exist の前に does が来ているが、これは強調の助動詞としての働き. 「もし、使用可能な理論が本当に実際に存在するのなら・・・」の意を表す. Ex. I do like studying English. (僕は英語の勉強が本当に好きなんだ.)
☆ ③ 文頭の however は接続副詞. where such theoretical criteria do not exist, では、where は関係副詞で場所・状況・局面などを表す際に用いられ、in the situation where…、in the circumstances where…や in the case where…のように表現される際に, where の1語で先行詞を含む形で実質上形容詞節(後置就職)と同じ働きをするものである. That is the house where I live. を That is where I live. 「あそこが僕が住んでいる家だよ。」「あそこが僕が住んでいるところだよ。」と表せる事を思い起こすことが出来るだろう. 同じように、That is where you are wrong. (TAISHUKAN’S English-Japanese Dictionaryより引用) 「そこが君の間違っている点だよ。」(TAISHUKAN’S English-Japanese Dictionaryより引用)とすることも出来る. このような場合での関係副詞の使い方では、 where は場所というよりも、「~の場合には」「~の点では」「~の局面に於いては」などの日本語訳がぴったりと当て嵌まる.
☆ ④ If this happens often, it will lead the writer・・・と、if 節で表現しているが、所謂仮定法ではなく、単なる条件節であることに注意(起こる確率が高い現象を表す際は、解放条件となり、直説法となる. 仮定法は、あくまでも在り得ない事或は事実ではない事を前提として条件節を作る表現方法である. コロン(:) 以下で前文を詳しく言換えしている. : he will always have his hands full and find it almost impossible to give・・・では、どちらの節も第5型式・SVOCの構文で、O = C (his hands = full, it = almost impossible で、 it = to give・・・と it は to give 以下を受ける) 目的語Oが補語Cの状態である事を示していることを要確認. ※仮定法については、Critical Analysis 6. 解説の~重要文法事項~を参照頂きたい.
☆ ⑤ 英文資料を読んでいる時、例えば、現在形の平叙文で記述されている中で、突如として助動詞の過去形表現に遭遇することがある. 助動詞の過去形には常に注意が必要である. このような場合は、著者は控えめな表現として表している. これを仮定法の婉曲表現という. 直截的にはっきりと述べるのではなく、控えめな・遠回しの表現にしている訳である. に ④文も当⑤文もif で始まる条件節になっているが、意味合いは少し変わる。④文では、If + S + V(現在形)、S + will + V・・・と、「しばしばこれが起こるのであれば、それは~であろう.」という現実味を帯びた表現であるので、これは直説法(仮定法ではなく)が、当⑤文は、条件節においても帰結節においても助動詞 would が使用されており、いずれも仮定法の婉曲表現ということになる. 但し、because 以下は理由は明らかであることから、遠回し表現にする必要もなく、直説法でありのままのことをそのまま述べている.
☆ ⑥ In short a working theory is an・・・・の working theory とは上述された内容の theory である者に取っては恣意的で、他の者に取っては納得のいかないような theory ではなく、ある意味、非の打ちどころがない理論で現実社会に於いて機能している健全な理論と解釈して良いと考える. そこで、本書では、この working theory を「実際に使える本来の理論」として「理論」としている.
☆ ⑦ Without such a theory, it is in general impossible for criticism to reach that point at which it becomes truly instructive―when its arguments are convincing and cannot be refuted.通常、代名詞や指示形容詞のついた名詞などは、既出のものに対して使われるものというのが一般的認識であろう. to reach that point では、指示形容詞 that は point を修飾しているが、決して既出のものに対する指示形容詞ではなく、後に関係代名詞が現れ、that が形容詞する名詞が先行詞になることを読み手側に予め教えるための働きがある.
Critical Analysis 2. 訳文
第1パラグラフ
① 外的な問題の他に、批判的研究は重大な内的困難に直面することにもなる。それは、戦争においては、1つの原因から結果が生じるということは殆どなく、つまり、通常は幾つかの同時発生的に起こる原因が存在するということである。
② 従って、どんなに正直で客観的立場に立とうとも、一連の出来事をその発生源にまで遡るだけでは不十分で、つまりは、それぞれの確認出来得る発生原因の1つ1つは正しく精査されねばならない。
③ そうすると、発生原因の本質についてより詳細な分析に至る事が可能になり、このようにして批判的研究を行う事で、私たちは本来の理論の領域へと足を踏み入れることが出来る。
④ 批判的考察、つまり、戦争で使われた手段を調査することで、その手段が使われたことによる特有な結果が何であるのか、その成果は手段が使用された当初の意図 (将帥がその手段を取った意図)と合致するのかについて疑問が投げかけられるのだ。
⑤ 使われた手段の特有の効果となると、我々はその手段の性質を研究することになり、換言すれば、また理論の領域へと足を踏み入ることになるのである。
⑥ 批判に於いては、議論する余地のない真理にまで到達する事が重要であることを確認してきた。従って、私たちは決して、他の者たちが受け容れないような恣意的な仮説で以て立ち止ってはならない。
第2パラグラフ
① 原因の究明と手段の検討が行きつくのは理論の領域、つまり、単なる個別案件の研究からでは推し量れない普遍的真理に行き着く、ということも私たちはこれまでに確認して来た。
② 使用可能な理論があるのなら、批判的考察はその理論に合致する結論を引合いに出せるので、その時点で研究を打ちとめに出来る。
③ しかしながら、そのような理論的基準が確立されていない場合には、批判的分析は基礎的要因に行き着くまでに推し進めねばならない。
④ もし時として、このような研究継続の必要が生じるであれば、研究者は入り組んだ迷路のようなものに入り込んでしまう事になる。つまり、彼は仕事で手一杯になり、要所要所於いて求められる 説明が出来なくなり、結果として、自分の研究に制限を課すために、結局は恣意的な主張で以てして探求を諦めなくてはならなくなるのである。
⑤ 例え、彼にとっては自身の研究は恣意的に見えないかも知れないが、他の者にとっては恣意的なものに映るだろう。何故なら、それらは自明の理でもなければ、証明されている訳でもないからである。
⑥ 要は、曖昧な解釈が可能なものではなく、恣意的要素のない理論こそが批判のための本質的基盤なのである。⑦ そのような理論が無ければ、一般的に批判が有意義たることはあり得ないだろう―つまり、恣意的でなくブレない理論があって初めて議論は説得力を持つものになり、応じて反駁を許さないのである。