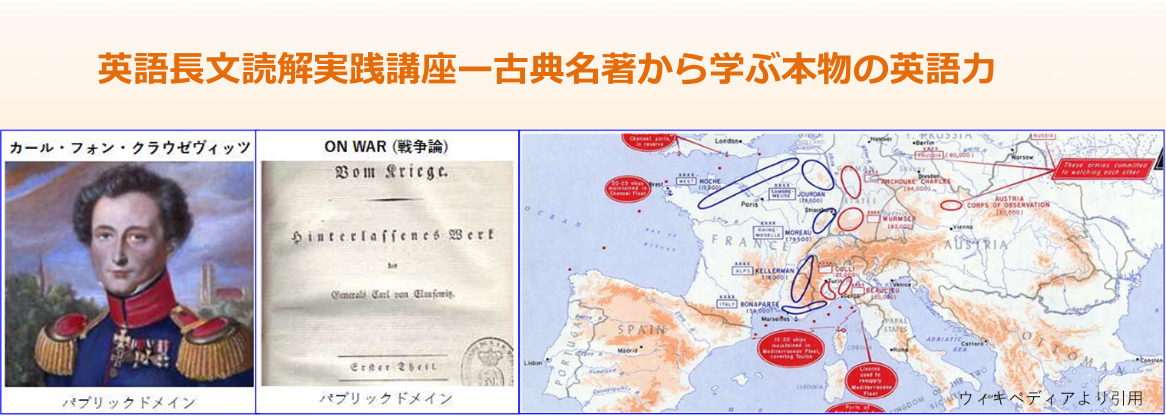Critical Analysis 6. 原文
There the French were so decisively superior in numbers-130,000 against 80,000-that the issue would not have been much in doubt. But then the question would again have arisen, what use would the French Directory have made of the victory? Would the French have pursued their advantage to the far frontiers of the Austrian monarchy, breaking Austrian power and shattering the Empire, or would they have been satisfied with the conquest of a sizable part of it as a surety for peace? We have to ascertain the probable consequences of both possibilities before determining the probable choice of the Directly. Let us assume that this consideration led to the answer that the French forces were far too weak to bring about the total collapse of Austria, so that the mere attempt to do so would have reserved the situation and even the conquest and occupation of a significant segment of Austrian territory would have placed the French in a strategic situation with which their forces could hardly have coped. This argument would have colored their view of the situation in which the Army of Italy found itself, and reduced its likely prospects. No doubt this is what persuaded Bonaparte, although he realized the Archduke’s hopeless situation, to sign the peace of Campo Formio, on conditions that imposed on the Austrians no greater sacrifices than the loss of some provinces which even the most successful campaign could not have recovered. But the French could not have counted even on the moderate gains of Campo Formio, and therefore could not have made them the objectives of their offensive, had it not been for two considerations. The first was the value the Austrians placed on the two possible outcomes. Though both of them made eventual success appear probable, would the Austrians have thought it worth the sacrifices they entailed-the continuations of the war-when that price could have been avoided by concluding a peace on not too unfavorable terms? The second consideration consists in the question whether the Austrian government would even pursue its reflections and thoroughly evaluate the potential limits of French success, rather than be disheartened by the impression of current reverses?
The first of these considerations is not simply idle speculation. On the contrary, it is of such decisive practical importance that it always arises whenever one aims at total victory. It is this which usually prevents such plans from being carried out.
The second consideration is just as essential, for war is not waged against an abstract enemy, but against a real one who must always be kept in mind. Certainly a man as bold as Bonaparte was conscious of this, confident as he was in the terror inspired by his approach. The same confidence led him to Moscow in 1812, but there it left him. In the course of gigantic battles, the terror had already been somewhat blunted. But in 1797 it was still fresh, and the secret of the effectiveness of resisting to the last had not yet been discovered. Still, even in 1797 his boldness would have had a negative result if he had not, as we have seen, sensed the risk involved and chosen the moderate peace of Campo Formio as an alternative
第1パラグラフ
※語・句注釈
*① there (副詞) = 文頭、文末で「その点で、そこで」 *② French Directory (固有名詞) = 「フランス総裁政府」1789年7月14日~1795年8月22日までのフランス革命後の新たな行政府とで1795年11月2日~1799年11月10日まで続いた *③ frontier (名詞) = 「辺境、国境、限界」 *③ surety (名詞) = 「保証、保証人、担保、抵当」 *④ ascertain (動詞) = 「確かめる、突き止める」 *⑤ reverse (動詞) = 「ひっくり返す、逆にする、立場を変える」 *⑤ significant (形容詞) = 「重要な、重大な」 *⑥ likely (形容詞) = 「あり得る、起こりそうな、もっともらしい、適切な、見込みのある」 *⑥ prospects (名詞・prospect の複数形) = 「展望、希望」 *⑩ entail (動詞) = 「~を伴う、引き起こす、~を含む、~を課す」 *⑪ consist in ~ (熟語動詞) = 「~から成る、~の組成から成る」 *⑪ dishearten (動詞) = 「勇気を失わさせる、落胆させる」be disheartened 受動態で「落胆する」
第2パラグラフ
※語・句注釈
*① idle (形容詞) = 「価値のない、無意味な、怠けている」 *① speculation (名詞) = 「思索、空論、根拠のない推測、投機」 *② on the contrary (前置詞句-副詞の働き) = 「それどころか」 *③ prevent A from B (熟語動詞) = 「AをBから妨げる」 *④ keep ~ in mind = 「~を心に留めておく、~を覚えておく」 *⑥ inspire (動詞) = ここでは受動態で使われている「鼓舞する、勘定を抱かせる、引き起こす、生じさせる」 *⑦ gigantic (形容詞) = 「巨大な、大きな」 *⑦ blunt (動詞) = 「思考力や感覚などを鈍らせる・弱くする、刃先などを鈍くする」⇔ sharpen
Critical Analysis 6. 解説
第1パラグラフ
① There the French were so decisively superior in numbers-130,000 against 80,000-that the issue would not have been much in doubt. ② But then the question would again have arisen, what use would the French Directory have made of the victory? ③ Would the French have pursued their advantage to the far frontiers of the Austrian monarchy, breaking Austrian power and shattering the Empire, or would they have been satisfied with the conquest of a sizable part of it as a surety for peace? ④ We have to ascertain the probable consequences of both possibilities before determining the probable choice of the Directly. ⑤ Let us assume that this consideration led to the answer that the French forces were far too weak to bring about the total collapse of Austria, so that the mere attempt to do so would have reversed the situation and even the conquest and occupation of a significant segment of Austrian territory would have placed the French in a strategic situation with which their forces could hardly have coped. ⑥ This argument would have colored their view of the situation in which the Army of Italy found itself, and reduced its likely prospects. ⑦ No doubt this is what persuaded Bonaparte, although he realized the Archduke’s hopeless situation, to sign the peace of Campo Formio, on conditions that imposed on the Austrians no greater sacrifices than the loss of some provinces which even the most successful campaign could not have recovered. ⑧ But the French could not have counted even on the moderate gains of Campo Formio, and therefore could not have made them the objectives of their offensive, had it not been for two considerations. ⑨ The first was the value the Austrians placed on the two possible outcomes. ⑩ Though both of them made eventual success appear probable, would the Austrians have thought it worth the sacrifices they entailed-the continuations of the war-when that price could have been avoided by concluding a peace on not too unfavorable terms? ⑪ The second consideration consists in the question whether the Austrian government would even pursue its reflections and thoroughly evaluate the potential limits of French success, rather than be disheartened by the impression of current reverses?
☆ ① so ~ that・・・構文、「~なので・・・である」と程度の意を表す. -(ダッシュ)と―(ダッシュの間に語・句を挟み込み、補足的説明を付け加えている場合が多い. 文頭の there は副詞の there. There, とコンマと打ったほうが、明瞭になるかとは思われる.
☆ ③ 仮定法過去完了の帰結節が疑問文になった形. 仮定法過去完了の帰結節は、過去の事実に反する条件に対しての想定を述べるので、訳は殆どの場合「~していたであろう」となる. これが単に疑問文の形になるので、そのまま疑問文のように訳して問題ない. breaking 以下は分詞構文なので主語は主節の the French.
☆ ⑤ Let us assume that this consideration led to the answer that・・・は、「仮にthat・・・以下であったとしよう」と、ここでは2つの仮説を提示している. that 節は answer に掛かる同格名詞節で、しかもその内容は仮説であることから直説法ではなく、助動詞過去形の would を使った仮定表現になっていることを要確認. 繰り返しになるが、⑤文目以降、このパラグラフでは全てが現実に反する仮定を基に議論がなされていることに注意. even the conquest and occupation of a significant segment of Austrian territory would have placed the French in a strategic situation with which their forces could hardly have coped. の with which their forces hardly have coped の個所は、cope with (熟語) = 「対処する、対応する、切抜ける」の with が関係代名詞 which の前に出た形で、先行詞は a strategic situation.
☆ ⑥ This argument would have colored their view of the situation in which the Army of Italy found itself, and reduced its likely prospects. This argument は上述の Let us assume that this consideration led to the answer の言い換えに充たるので、this argument だけで仮定法過去完了の条件節を含意しており、意味としては上述より、「考察がこのような答えに至ったとすれば」等と理解することが出来る. ということで、当文で仮定法の条件節と帰結節が合わさっているものと考える (例: A man of integrity wouldn’t say such a thing. 「誠実な人ならば、そんな事は言いはしないだろう。」主語 A man of integrity に仮定法条件節に相当する意味合いが含まれている). color one’s view of ~ で「~に影響を与える、~の見方をゆがめる」などという意味を表す.
☆ ⑧ 文末に位置し、コンマ(,) の後の had it not been for two considerations. は仮定法過去完了の条件節の倒置であることを確認. 「もしも2つの考慮すべきものが無かったとしたならば」の意を表す. 但し、この2つの考慮すべきものとは、以下に述べるオーストリア軍側の考慮・考察のであることに注意.
☆ ⑩ 学校英語では、when と完了形は1文内に同居出来ないと教わる. 受験英語だけに関して言えば、それに従ったほうが良い. 但し実際の英文資料などでは、完了形と when が同一文内に存在するケースは多々あるのが実情である. 辞書で when を調べてみれば判ると思うが、when が接続詞で副詞節を導く場合、「~なのに」や「~だけれども」のように【対照・譲歩】を表す場合には、完了形と一緒に使われる場合もあることを知っておくのは予備知識と役に立つものである.
Ex.1: Why did he abandon it, when he might have succeeded? 「彼は成功したかも知れないのに、何故それを放棄したのだろうか?」
Ex.2: She can go to work when her kids have gone to school. 「彼女の子供達は学校に行ったので、仕事に出掛けられる。」などである. 通常、when を接続詞として使用する副詞節では時間軸の中である1点を示す際に使用される. 例えば、When I was 32, I started to study politics. では「私は32歳の時、政治学を勉強し始めた。」と時間軸の中でのある1点の起点の起点を表す. When you have finished studying the basics of politics, you can run for election. would the Austrians have thought it worth・・?の have thought it worth は S + V + O + C の第5形式の表現.
☆ ⑪ consist in は語・句注釈通りで「~の要素に存する」の意.
第2パラグラフ
① The first of these considerations is not simply idle speculation. ② On the contrary, it is of such decisive practical importance that it always arises whenever one aims at total victory. ③ It is this which usually prevents such plans from being carried out.
④ The second consideration is just as essential, for war is not waged against an abstract enemy, but against a real one who must always be kept in mind. ⑤ Certainly a man as bold as Bonaparte was conscious of this, confident as he was in the terror inspired by his approach. ⑥ The same confidence led him to Moscow in 1812, but there it left him. ⑦ In the course of gigantic battles, the terror had already been somewhat blunted. ⑧ But in 1797 it was still fresh, and the secret of the effectiveness of resisting to the last had not yet been discovered. ⑨ Still, even in 1797 his boldness would have had a negative result if he had not, as we have seen, sensed the risk involved and chosen the moderate peace of Campo Formio as an alternative.
☆ ① be not simply C (補語) で、否定語 not よりも後ろの (右側) 表現を否定しており、simply は否定を強調する役割として機能している.
☆ ② it is of such decisive practical importance that it always arises whenever one aims at total victory. ポイントは2つ. 1つ目は、of such decisive practical importance で、英語では of + 抽象名詞で、形容詞・形容詞句の働きをする. これらの表現には数に限りがあるので予めある程度覚えておくことをお勧めする. ある程度一覧を以下記す、参考にして頂ければ幸いである.1) of importance = important 「大切な、重要な」 2) of no help = helpless 「無力な、無能な、絶望的な」 3) of great value = very valuable 「非常に重要な、価値のある」 4) of no use = useless 「無用な、まったく役に立たない」 5) of worth = worthy 「価値のある」 6) of great significance = very significant 「とても重要な」 前置詞 of には、~の性質・性格を有する、という意味合いがある. 2つ目は、such ~ that・・構文で「~なので・・である」接続詞に関わる個所である. such ~で程度を表し、that 以下でその程度がどの程度なのかの内容を示す. この観点より、程度を表す so that 構文に極めて近い働きがある. 当文であれば、第1の考察は決定的な実践上の重要性になるので、完全勝利を目指す場合は常にこの考察が出てくる、というもので、訳し上げれば、完全勝利を目指すときは常に第1の考察が出てくるほど、決定的な実践上の重要性がある、ということである. It is so decisive practical an importance that it always arises・・となる. ここでついでに、so that 構文と such that 構文との大きな違いにも触れておく. so は副詞なので名詞を修飾することは出来ないので形容詞を後に置いて名詞に繋げるが、such は形容詞なので後に名詞を持ってくることが出来る. また冠詞の位置にも注意が必要になる.
Ex.1: He is so wise a man that everyone asks for advice.
Ex2: He is such a wise man that everyone asks for advice.such that 構文は、程度を表す so that 構文に近い意味を表す(因みに、so that 構文には他にも、目的を表す場合、結果を表す場合の用法がある)ここで、協調構文について簡単にまとめておくので、英文解釈・英語長文読解上重要なので、以下記しておく. 前提としては、it is ~ that・・・構文である. 「・・・するのが ~ である」「~こそが・・・する」の意味になるのが強調構文である.
☆ ③ 強調構文の表現. よくある形は、it is ~ that・・・で、~ の部分を強調する表現であるが、which も同じように強調構文で使われる. 当文では this が強調されており、そこに that を使うと並びも厄介なので、it is ~ which・・・の形が使用されているだろうと考えられる. this は既述の第1の考察のこと.
☆ ④ The second consideration is just as essential (as the first one 若しくは consideration) と括弧内を補って読む. for は理由を表す接続詞として使われている.
☆ ⑤ confident as he was in the terror inspired by his approach. 程度などを示す形容詞・副詞或いは名詞を前に置き、その後に as S + be 動詞 で表す譲歩の用法. Bis as he was, he could not win. で「彼は大きかったが、勝てなかった。」などの意を表す. ここでは「彼が接近することで生じさせられる恐怖の念に彼は自信があった」が直訳になる. 訳文では意訳を施してある.
☆ ⑨ 仮定法過去完了の文. if he had not, as we have seen, sensed the risk involved and chosen the moderate peace of Campo Formio as an alternative. の部分は if he had not sensed the risk involved は 等位接続詞 and で結ばれているので、and (had not) chosen the moderate peace of Campo Formio as an alternative. と否定部分を補ってよむこと. 文頭の still は、「それでもなお、それにもかかわらず」の意を表す.
~重要文法事項~
仮定法について
仮定法は、英語の学習の中で最も難しい単元の1つだ. 時として、仮定法という言葉自体が誤解をも生んでいる節もある. 先ず、仮定法で押さえておかなくてはならないのは、仮定法とは、人の心情・気持ちを表すもので、事実ではない事・非現実の事を述べる時の動詞の使用方法 (現在・過去・過去完了等) であるということ. 現実と非現実 (或は事実とは異なること) との乖離が動詞の時制ずれになって表現される. 仮定法では、ある事柄について、現実(或は事実)とは異なることを正に仮定或は仮想し、それを条件節として表し、その仮定・仮想条件に基づいて、非現実 (事実とは異なること) を想定して帰結節 (主節) で述べている. 現実と非現実の仮定・仮想が、正に人間の心情・心象に直結するもので、その心情・心象が動詞の形になって現れるという事である. 人間1人1人の心の中には、現実には無理と解っていてもどうしても理想を描いたり、切望・願望したりする一方、自身で行ったことに対して、そうしなければ良かったなどの後悔の念、他の方法でやるべきだったなどと今となっては遅いがそうすべきだったなどの自責の念などが沸き起こる事もある. そのような心情・心象を表す際に仮定法が使用される.
.仮定法とは、非現実の事柄に言及する際の表現及び動詞の使用方法であるが、ここで言う非現実とは、①事実と異なる事、②全くの願望で実現する可能性が極めて少ないと予めわかっていること、である. 文は条件節と帰結節からなる. 条件節では ifで非現実の条件が設定され、 帰結節ではその非現実の条件設定に基づいた非現実の想定を述べているのである.その時に使用する動詞の形 (条件節及び帰結節共に) を仮定法と言い、これが仮定法のつかう際のこころの状態を表す. ここをしっかりと押さえて頂きたい.重要な事は、“if が使われているから仮定法だ”ということではないということ. if 節の中で使われている動詞の形(過去形なのか過去完了形なのか現在形なのか)である. 仮定法理解で重要なのは、書かれてある内容、話されている内容が現実の事なのか、或は現実には起こり得ないものなのか、という事である.別の言葉で言えば、実現する可能性の有無なのである. 現在の状況について述べるであれば、それは現状の事実なのか、それとも実現する可能性がないと分かっている単なる願望・仮想なのか、ということである. 過去の状況について述べるのであれば、過去の事実に照らしてその条件は事実なのか、それとも過去の事実とは異なる条件設定或は願望・想定なのか、という事である.
仮定法に関わる重要事項として以下7項目を挙げる.
1.仮定法過去
2.仮定法過去完了
3.仮定法現在
4.助動詞による婉曲表現
5.条件節の意味内容が未来に言及する場合
6.実現する可能性のあるif節は単なる条件文で仮定法ではなく、直説法である
7.仮定法のいろいろな条件節相当語句
1.仮定法過去の用法: 仮定法過去では、現在の非現実の事柄を設定して、その非現実の条件設定に対して、非現実の想定を帰結節で表す.
仮定法過去形の基本例: If + S + V過去形・・, S + 助動詞過去形(would, could, mightなど) + 原形動詞・・.
(帰結節が受身の場合、S + 助動詞過去形(would, could, might等) + be + 過去分詞)
Ex.1: If I had free time, I could take Koro for a walk. 散歩する = take a walk
「もし時間があれば、コロを散歩に連れて行けるのになぁ」現在やることが一杯で時間がなく、愛犬のコロを散歩に連れていけない状態、を示している.
現在忙しい状況において、「時間があればなぁ」という非現実を条件設定をしている. そこで、帰結節ではこの非現実の条件設定に基づいて、実際にはコロを散歩には連れていけないが、「散歩に連れていけるのになぁ」という非現実の想定を述べている.
Ex.2: If I were (was) in your shoes, I would never tell a lie to the boss. 立場にある:be in one’s shoes
「もし私があなたの立場だったら、上司に嘘をついたりはしないだろう」 同僚が失敗して、上司に嘘を報告している場面、を示している.
纏め: If 節の意味内容が現在の事実に反する時は、時制を現在から過去に1つずらし表現する. If の条件節では動詞は過去形を用い、帰結節では助動詞過去形 + 原形動詞を使う.
2.仮定法過去完了の用法: 仮定法過去完了では、過去の非現実の事柄(事実とは異なる)を条件設定して、その過去の事実に反する・非現実の条件設定に対して、過去の事実とは異なる想定を帰結節で表す.
仮定法過去完了の基本形:
If + S + had + pp・・, S + 助動詞過去形 (would, could, might等) + have + 過去分詞・・
.(帰結節が受身の場合、S + 助動詞過去形 + have + been + 過去分詞・・.)
Ex.1: If the ambulance hadn’t arrived so quickly, the boy would have died.
「もし救急車がそんなに早く来てくれなかったら、少年は死んでしまっていただろうに」
救急車が本当に早く来てくれたおかげで、少年が助かった、という場面を示している.
Ex.2: If Tom hadn’t cheated, he wouldn’t have passed the exam.
「もしトムはカンニングしていていなかったら、試験に受かってなかっただろうね。」
トムはカンニングをしたので試験に合格することができた、ことを示している.
又、過去の事実に反する事柄を条件設定し、その事が現在にまで影響を及ぼしている場合には、下記Ex.3のようになる.
Ex.3: If he had not studied hard at that time, he would not be a college student by now.
「もし彼はあの時一生懸命勉強しなかったならば、彼は今頃大学生ではないだろう。」
彼はあの時一生懸命勉強したので現在大学生でいられる状態、を示している.
この文では、過去の事実に反する仮定が現在まで影響を及ぼしていることから、帰結節では、通常の would have + 過去分詞 or would have + been + 過去分詞ではなく、単に助動詞過去形と原形動詞の would not be a student (この場合は否定形になっている)で表されている.
3.仮定法現在の用法: 2つの形がある. ①特定の一般動詞(要求・提案・決定などに関する)及び②形式主語構文 it を用いる it is 形容詞 that ・・で表す形がある(この場合の形容詞で多いのはnecessary、important、essentialのような形容詞がある). 仮定法現在で共通しているのは、that節内で使用される動詞は原形であるということ(但し、イギリス英語では原形動詞の前にshouldを置くことになっている者の現在では必ずしもshouldを置かない用途も出てきている: 言語は時代と共に活用の仕方が進化?或は変化しているものなので、そこは時代の変化を意識しながら言語に取組むということになるのだと考える).
① 特定の一般動詞の場合: S + V(特定の動詞) that S + 動詞の原形. demand, insist, require (要求する、insist には主張するの意味もあるが、主張するを意味する場合には仮定法現在の用法はない), suggest, propose, recommend (提案する) 等の意味を示すもの. 似通った動詞群があり、紛らわしくはあるが、使われる動詞には数限りがあるので、予めある程度これらの動詞を覚えておくのをお勧めする.
Ex.1: The board of directors demanded that the meeting (should) be held immediately.
Ex.2: He insisted that she (should) be dispatched to the United States.
Ex.3: They proposed that the boss (should) make a presentation to the prospective customer.
② It is 形容詞 that S + be動詞・・の形の場合: 形容詞を用いて間接的に要求や願望の意を示す. ①の特定の一般動詞と同じく、この用法で使われる形容詞は大体決まっており、necessary, important, advisable, desirable, essential, urgent等があるが、予めある程度これらの形容詞を覚えておくのをお勧めする.
Ex.1: It is necessary that all the passengers (should) be evacuated right away.
Ex.2: It is important that they (should) make a final decision.
4.助動詞の過去形使用による婉曲表現
仮定法のなかに婉曲表現というものがある. 婉曲表現では、直接的にものを言ったり、断定的な表現を避けるものである. 同じように英語でも、直截的な表現を避け、遠回しに表現をする際には、助動詞の過去形を使う. 仮定法過去では現在の事実に反する事柄を、そして仮定法過去完了では過去の事実に反する事柄を表現している訳であるが、現実と非現実との差が、使用する動詞の時制をずらす事で表現者の心情が表されていることを学んだ. 婉曲表現でも同じことが当て嵌まる. 遠回しで述べる、断定的な言い回しを避けようとする表現者の心情が、本来原形動詞による直説法で表すことが出来るものを、助動詞の過去形に原形動詞をつけるという表現に現れているのである. 例えば、以下、AさんとBさんのやり取りを見てみる.
A: What do you think of his opinion?
B: I would agree with what he said.
Bさんの、I would agree with what he said.では、I agree with what he said.とは賛同 (agree) する度合いが異なる事を意味する. I agree with what he said.では、何の躊躇もなく「彼の言った事には賛成です。」の意味になるが、I would agree with what he said.では、「どちらかと言えば、彼の言った事には賛成です。」と控えめな表現になる. Bさんには断定的に自信を持ってはっきりとは言えないという心情 (心の在り様) がある為に、本動詞agreeの前に、賛同する (agree) 度合いを抑える為に、助動詞の would で表現しているのだ. この仮定法の婉曲表現は、あらゆる英文を読む際、 非常によく出て来るので、文章全体が過去の事柄を述べていないのに突然に助動詞の過去形(would, could, might等)が出て来る場合には、過去形の意味としての解釈が腑に落ちない際には、婉曲表現ではないかと気づいて貰いたい.
5.条件節の意味内容が未来に言及する場合: 2つの場合に分けて考える必要がある.
If 節の条件節で、将来において予め起こり得る可能性が予め低い (実現する可能性が低い )と分かっている内容を表現する際には、should や were toを使う. were to の場合は①実現の可能性が少なく、加えて②望みようもない事柄に使う傾向がある.
Ex.1: If it should rain tomorrow, we will call off the meeting.
もし、明日雨が降るようであれば、会議は中止にしよう.
(実際には、予報では晴れになっているので、「万が一、雨がふれば」の意を表す)
Ex.2: If the project should fail in the future, we would be put out of jobs.
万が一、そのプロジェクトが失敗するようなことになれば、私たちは職を失うだろう.
(実際には、プロジェクトが成功すると思っているので、職を失うことはないと、考えている.
Ex.3: What would you do if war were to break out? If S should Vよりも強意を表す.
万が一、戦争が起きるとすると、どうされるおつもりか.
(実際には、戦争なんて起きはしないだろうという前提で、使われている)
しかし、現在の世界の状況を見渡してみると、、かなりの確率で戦争は起きそうな様相を呈してきている. そうすると、if war were to break out, という仮定法ではなく、6.で述べる開放条件に当て嵌まる可能性も出て来ると言える.
6. 開放条件 ( 直説法で仮定法ではない )
仮定法は実現する可能性が極めて少ない事柄・非現実を仮想する時の表現であることを学んできた. 一方で、現実社会の普段の生活の中では、実現する可能性があることを仮定する場合がある. このような実現する可能性がある事柄をif節で条件提示する場合は仮定法にはならない. 通常の直説法の表現となる. つまり、実現する可能性のあるif節は単なる条件文で仮定法ではなく、直説法である. これを開放条件という. 例えば、単なる事実の条件提示だったり、条件提示が五分五分の確率で起こり得そうと考えられる条件文では開放条件のif節が使われる. 繰り返しになるが、これは仮定法ではなく、直説法となる.
Ex.1: If you lie on the beach under the strong sunlight for too long, you get sunburnt.
強い日差しの中で長い時間ビーチに横になっていると、日焼けするよ.
Ex.2: If you turn right there, you will see him dancing there.
そこを右に曲がると、彼が踊っているのが見えるよ.
Ex.3: If you submit a false report to your boss, I think that you will get scolded.
もしあなたが間違った報告をすると、怒られると思うよ.
上記a)・b)・c)は全てif節を使った条件節ではあるが、仮定法で言われる事実の反する事・非現実の事・実現する可能性が殆どない事を表現しているのではなく、当たり前の事であったり、十分に可能性があることを表現しているわけで、仮定法ではない. これらを開放条件という.
7.ifを使わずに仮定法条件節を表す表現 (条件節相当語句の表現)
仮定法の条件節相当語句とは、仮定法でのifを使用せず、仮定法条件節を示す表現のことである. to不定詞句・分詞句・副詞句・条件を含む主語の使用・接続詞によるその他の表現などがある.
1. to不定詞句
Ex.1: You would be unwise to believe what he says simply because he is a lawyer.
弁護士であるからという理由だけで、彼の言う事を信じるなんては賢明ではない.
to believe は判断の根拠を示す to 不定詞の副詞用法で、would be unwise で仮定法が使われている.
= If you were to believe what he says simply because he is a lawyer, you would be unwise.
Ex.2: To hear him speak, you would take him for a native English speaker.
彼が話しているのを聞けば、ネイティブイングリッシュスピーカーだと間違えるだろう.
= If you heard him speak, you would take・・.
2. 分詞句
Ex.1: Knowing a little more about it, I would not be here right now.
もう少しでもそのことを知っていれば、今頃私ははそこにいるだろうに.
= If I knew a little more about it, I would be there by now.
3. 副詞及び副詞句
Ex.1: But for language we would have no means of verbal communication.
もし言語がないとしたら、私たちは言葉によるコミュニケーション手段を持っていないだろう.¬
= If it were not for language we would have no means of verbal communication.
Ex.2: Without your support I could have never completed the project.
もしあなたのサポートが無かったならば、私はそのプロジェクトを完結出来なかっただろう.
= If it had not been for your support, I could not have completed the project.
Ex.3: With a little more courtesy you could be accepted by more supporters.
もう少しで礼儀正しがあれば、もっと多くの支持者の方々に受け容れて貰えるだろうに.
= If there were a little more courtesy, you could be accepted by more supporters.
Ex.4: He came down with a cold; otherwise, he might have won the election.
彼は風邪を引いてしまった. でなければ、彼は選挙で当選していただろうに.
= If he had not come down with a cold, he might have won the elections.
4. 条件を含む主語
Ex.1: A considerate person would not have made such remarks on the stage.
思いやりのある人だったら壇上でそんな事は口にしなかっただろうに.
= If he(she) had been a considerate person, he (she) would not made such remarks.
Ex.2: A more experienced candidate would have taken the other tactics.
もっと経験豊富な候補者だったならもう1つの戦術をとっていただろうに.
= If he had been a more experienced candidate, he would have taken the other tactics.
5. 接続詞のよるその他の表現
Ex.1: Suppose (supposing) that your teacher found you here, what would he say?
もし先生が君がここにいるのを見つけたら、なんというだろうか.
= If your teacher found you here, what would he say?
※provided (providing) that・・にも「もし~だとしたら」の意があるが、provided that・・は直説法のみに使用される. 一方で、suppose (supposing) that・・仮定法でも直接でも用いられる.
Critical Analysis 6. 訳文
第1パラグラフ
① その点、フランス軍は数に於いて決定的に優勢だったので―オーストリア軍の80,000兵に対して130,000-、フランス軍の勝利に疑いを差し挟む余地は無かった。
② しかし、また新たな疑問が想起されよう. つまり、 フランス総裁政府はこの勝利をどのような目的で利用しようとしたのであろうか。
③ フランス総裁政府は、オーストリア大公国の国境地帯まで彼らの優勢を追い求めて、オーストリア軍を打破し、帝国を完膚なきまでに打ち砕くつもりだったのだろうか?それとも、講和の為の抵当物件として国土のかなりの部分を占領することに酔いしれていたのだろうか?
④ 総裁政府の取り得る選択肢を決定する前に、上述2つのどちらの可能性からも生じ得る結果を確かめなくてはならない。
⑤ この考察が以下のような仮定に至ったとしよう。フランス軍の力では、オーストリア軍に壊滅的崩壊をもたらすには全く不十分なので、ただ単にそのような壊滅を試みるような行為はフランス軍の優勢とオーストリア軍の劣勢を逆転させ得たかも知れないし、オーストリア国土の重要な部分を征服し占領保持することすらフランス軍の戦力では到底その状態を持ち堪えることはできないような戦略的立場にいたであろう、と。
⑥ これが答えであったとすれば、そこにいるナポレオンのイタリア遠征軍にも影響を与えていたであろうし、彼らの希望も減じられていたであろう。つまり、これは軍隊の中の士気の低下に繋がるのである。
⑦ ナポレオンはオーストリア軍のカール大公の絶望的な状況を知っていたが、上述の考察があったからこそカンポ・フォルミオの条約を締結したのは間違いないだろう. それを表すのが、この条 約によってオーストリアに課せられたのは、例え今後の戦役でオーストリアが勝利を収めることが出来たとしても奪還出来そうにはない数州の犠牲のみに留まったことである。
⑧ しかし、もし以下に述べるオーストリア側の2つの考察がなかったとしたら、フランス軍はカンポフォルミオの控えめな利益、つまり、オーストリアの数州の獲得すらも期待出来なかっただろうし、この獲得を攻撃の目的にすら出来なかったかも知れない。
⑨ 先ず、第1の考察は、フランス軍によるオーストリア軍の壊滅が形勢を逆転させていたかも知れず、フランス軍の占領は長くは続きようが無かったであろうという2つの可能性に対して、オーストリア軍が如何なる価値を置いていたかである。
⑩ どちらの考察でも、オーストリア軍が最終的には勝利を収める可能性はあったようには見えたが、それほど不利ではない講和条約を締結することで代償を避けられたかも知れないのに、オーストリア軍は戦争継続に伴う犠牲にそれだけの価値があったとみなしていたであろうか?
⑪ 2つ目の考察は以下の問題である。つまり、オーストリア政府は、現下の逆境に影響を受け落胆するのではなく、熟考に熟考を重ねて、フランス軍の勝利の限界がどこにあるかを徹底的に調べ上げていたであろうかという問いであう。
第2パラグラフ
① 1つ目の考察はただ単に無意味な詮索などということではない。
② それどころか、この考察は決定的な実践上の重要性があるので、完全勝利を目指すときにはいつでもこの問いが出てくる。
③ またこのような考察こそが、完全勝利を目指すような計画が実行されるのを妨げるものである。
④ 2つ目の考察も1つ目の考察同様必須のものである。というのも、戦争というものは抽象的な敵と戦うのではなく、こちらとしては常に心に留めて置かなくてはならない現実の敵と戦うものだからである。
⑤ 確かに、勇猛果敢なナポレオンはこの点に気付いており、彼には、彼が進軍するだけで敵を恐怖に陥れるだけの自信があった。
⑥ 同じ自信により、ナポレオンは1812年にモスクワに行くことが出来たが、そこでは敵軍の彼に対する畏怖の念が離れてしまった。
⑦ ロシアとフランスの間の巨大な戦争の中で、敵軍のナポレオンに対する恐怖の念の幾分か薄らいでしまっていた。
⑧ しかし、1797年には彼に対する畏怖の念はまだ新鮮で、当時は徹底抗戦の有効性についての秘訣というものがいまだ見出されてはいなかった。
⑨ それにもかかわらず、1797年でさえも、すでにみてきたように、当時ナポレオンがもし勝利していたオーストリア軍に依る逆襲の危険を感知せず、その代替案として緩い条件でのカンポ・フォルミオ条約締結に打開策を見出していなかったならば、彼の勇猛果敢さは裏目に出て悪い結果をもたらしていたことであろう。