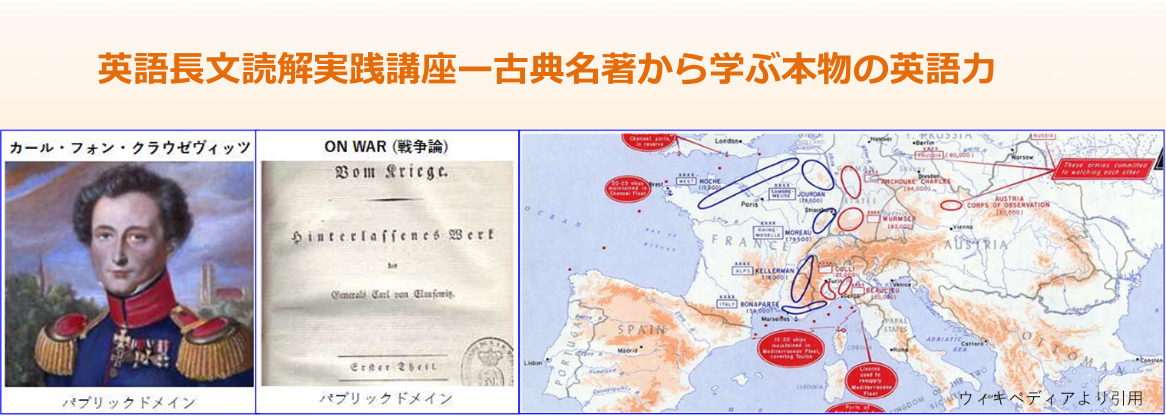Critical Analysis 4. 原文
The business of critical analysis and proof is not very difficult in cases of this kind; it is bound to be easy if one restricts oneself to the most immediate aims and effects. This may be done quite arbitrarily if one isolates the matter from the setting and studies it only under those conditions. But in war, as in life generally, all parts of a whole are interconnected and thus the effects produced, however small their cause, must influence all subsequent military operations and modify their final outcome to some degree, however slight. In the same way, every means must influence even the ultimate purpose. One can go on tracing the effects that a cause produces so long as it seems worth while.
In the same way, a means may be evaluated, not merely with respect to its immediate end: that end itself should be appraised as a means for the next and highest one; and thus we can follow a chain of sequential objectives until we reach one that requires no justification, because its necessity is self-evident. In many cases, particularly those involving great and decisive actions, the analysis must extend to the ultimate objective, which is to bring about peace. Every stage in this progression obviously implies a new basis for judgment. That which seems correct when looked at from one level may, when viewed from a higher one, appear objectionable.
In a critical analysis of the action, the search for the causes of phenomena and the testing of means in relation to ends always go hand in hand, for only the search for a cause will reveal the questions that need to be studied. The pursuit of this chain, upward and downward, presents considerable problems. The greater the distance between the event and the cause that we are seeking, the larger the number of other causes that have to be considered at the same time. Their possible influence on events has to be established and allowed for, since the greater the magnitude of any event, the wider the range of forces and circumstances that affect it.
When the causes for the loss of a battle have been ascertained, we shall admittedly also know some of the causes of the effects that this lost battle had upon the whole―but only some, since the final outcome will have been affected by other causes as well. In the analysis of the means, we encounter the same multiplicity as our viewpoint becomes more comprehensive. The higher the ends, the greater the number of means by which they may be reached. The final aim of the war is pursued by all armies simultaneously, and we therefore have to consider the full extent of everything that has happened, or might have happened. We can see that this may sometimes lead to a broad and complex field of inquiry in which we may easily get lost. A great many assumptions have to be made about things that did not actually happen but seemed possible, and that, therefore, cannot be left out of account.
第1パラグラフ
※語・句注釈
*① be bound to be (成句的表現) = 「するようになっている、縛り付けられている、~する運命にある」 *② arbitrarily (副詞) = 「恣意的に、勝手に、独断的に」 (arbitrary (形容詞) = 「恣意的な、任意の、独断的な」) *③ ultimate (形容詞) = 「最終的な、究極の」 *⑤ so long as (接続詞) = 「~する限りは」3語で接続詞の働きをしていると考えて良い *⑥ a chain of ~(複数名詞・名詞句) = 「一連の、~の連鎖」 *⑥ sequential (形容詞) = 「連続的に起こる」 *⑦ bring about (句動詞) = 「~をもたらす、~を引き起こす」 *⑨ objectionable (形容詞) = 「異議のある、反対するべき」
第2パラグラフ
※語・句注釈
*① in relation to (前置詞句) = 「~に関して」 *① go hand in hand (熟語・成句的表現) = 「手と手を携えて行く、協同歩調を取る、連携する」 *② pursuit (名詞) = 「仕事、研究、追跡」*③ considerable (形容詞) = 「(規模・量などが)かなりの、相当な」 *⑤ admittedly (副詞) = 「明らかに、一般にも認められているように」 *⑤ 文末に置かれる as well (副詞句) = 「~もまた、同じように」 *⑥ viewpoint (名詞) = 「視点、立場、観点、見地」 *⑥ encounter (動詞) = 「たまたま遭遇する、偶然に出会う」 *⑧ simultaneously (副詞) = 「同時に」simultaneous interpretation = 「同時通訳」 *⑩ assumptions (名詞・assumptionの複数形) = 「想定、推定」
Critical Analysis 4. 解説
第1パラグラフ
① The business of critical analysis and proof is not very difficult in cases of this kind; it is bound to be easy if one restricts oneself to the most immediate aims and effects. ② This may be done quite arbitrarily if one isolates the matter from the setting and studies it only under those conditions. ③ But in war, as in life generally, all parts of a whole are interconnected and thus the effects produced, however small their cause, must influence all subsequent military operations and modify their final outcome to some degree, however slight. ④ In the same way, every means must influence even the ultimate purpose. ⑤ One can go on tracing the effects that a cause produces so long as it seems worth while.
⑥ In the same way, a means may be evaluated, not merely with respect to its immediate end: that end itself should be appraised as a means for the next and highest one; and thus we can follow a chain of sequential objectives until we reach one that requires no justification, because its necessity is self-evident. ⑦ In many cases, particularly those involving great and decisive actions, the analysis must extend to the ultimate objective, which is to bring about peace. ⑧ Every stage in this progression obviously implies a new basis for judgment. ⑨ That which seems correct when looked at from one level may, when viewed from a higher one, appear objectionable
☆ ① be bound to be (do) の bound は 他動詞 bind (縛る、束縛する、義務付ける) の過去分詞であると同時に形容詞としての働きもある. be bound to be (do) はある意味、成句的表現で「~するようになっている、~する運命にある、~する義務がある」という意を表す.
☆ ② if one isolates the matter from・・は非現実の仮定ではなく、直説法の条件節であることに注意. 所謂仮定法ではない. 直説法で表す if 条件節は、「もし・・」と理解するよりも、「~の場合は」とするほうが意味が通りやすい. また、if one isolates・・の one は総称人称の one の使い方で、はっきりと主語を訳す必要性はない. 主語を無理に表現しようとすると可笑しな日本語表現になるので、このような場合は、訳文にあるように事象の表現として理解するのが賢明と考える. ⑤文も同じく総称人称の主語として one が使われているので、ここも同じく主語をはっきりと示すのではなく、訳すのであれば一般概念化する形で事象として表すほうがよい.
☆ ③ as in life generally の as は前置詞としてでは無く接続詞の働きで、厳密には as (it is) in life generally と主語・述語が省略されている形と考えて良い. all parts of a whole are interconnected and thus the effects produced. however small their cause・・ では、however は「どんなに~であろうとも」と譲歩節を導く副詞で、however small their cause (is 或いは may be) と述語動詞が省略されていることが理解出来ると構文的にも意味的に解釈し易くなる。文末の however slight も同じく however slight (it is 或いは it may be) と主語と動詞が省略されていると読み取る. 因みに、ここでの it は outcome のこと. また、however には文と文を対照的に結ぶ接続副詞としての働きもある. 例: She didn’t want to go to London. However, the manager decided to dispatch her there. 「彼女はロンドンには行きたくなかった。しかしながら、上司は彼女をロンドンへと赴任させた。」 因みに、接続副詞には、however のような文と文を対照的に結ぶものもあれば、追加的補足説明をするような thus, furthermore, beside や、条件を示す otherwise などがある. 接続副詞として機能するものは数も20個 (20単語) 程度であるので、その都度都度で覚えるようにすれば良い.
☆ ⑤ One can go on tracing the effects that a cause produces so long as it seems worth while.原文のまま載せてある、現代英語では文末は、worthwhile としても良いだろう. 当文は英文そのもの自体は単純なものであるが、訳に於いては、これまでの流れを補完して訳さないと味気ないものになってしまう. これまで例題3でも、「戦争の因果関係と目的に対する手段の使用が適切であったかどうかを検証するのが批判の本務」であったので、たった1つに起因する原因から生じた様々結果 (effects)であっても、研究を行う価値があればそれを行うことは可能である、と説いている. そして、この流れは⑥文目にも続いて行く.
☆ ⑥ for the next and highest one の one は代名詞としての働きで end (目的) を受ける. 例題③の流れ、そして⑤文目の流れからも、当文は「手段は検討されるが、単に目の前の目的に関してだけでなく、その目的そのものが次なる高次の目的の為に検討されねばならず、このようにして初めて、一連の目的の連なり―それは単にある戦役においての勝利を得ることから究極目的である講和条件を結ぶということ―手段の正当性を主張する必要がない目的に至るわけである、何故なら、それはその時点ではもう自明の理となっているからである。」と内容を補って理解する.
☆ ⑦ those involving・・の involving 以下は現在分詞による後置修飾で前の those に掛かる. , which (カンマ + which) の which は継続用法の関係代名詞で、前節を受けて「そしてそれが平和に至るのである」を意味する. those involving・・・は、前の句の in many case と同格で many cases の説明個所になっている.
☆ ⑨ That which seems correct・・の that which は what と同義で、what seems correct whenlooked at from one level が名詞節で本文の主語. when looked at は when (it is) looked at の省略表現であることを要確認. 同じく、挿入節の働きになる when viewed from a higher one も when (it is) viewed from a higher one と主語・述語が省略されていると解釈する.
第2パラグラフ
① In a critical analysis of the action, the search for the causes of phenomena and the testing of means in relation to ends always go hand in hand, for only the search for a cause will reveal the questions that need to be studied. ② The pursuit of this chain, upward and downward, presents considerable problems. ③ The greater the distance between the event and the cause that we are seeking, the larger the number of other causes that have to be considered at the same time. ④ Their possible influence on events has to be established and allowed for, since the greater the magnitude of any event, the wider the range of forces and circumstances that affect it.
⑤ When the causes for the loss of a battle have been ascertained, we shall admittedly also know some of the causes of the effects that this lost battle had upon the whole―but only some, since the final outcome will have been affected by other causes as well. ⑥ In the analysis of the means, we encounter the same multiplicity as our viewpoint becomes more comprehensive. ⑦ The higher the ends, the greater the number of means by which they may be reached. ⑧ The final aim of the war is pursued by all armies simultaneously, and we therefore have to consider the full extent of everything that has happened, or might have happened. ⑨ We can see that this may sometimes lead to a broad and complex field of inquiry in which we may easily get lost. ⑩ A great many assumptions have to be made about things that did not actually happen but seemed possible, and that, therefore, cannot be left out of account.
☆ ① 当文の , for(コンマ + for)・・・の for は前置詞の for ではなく、コンマの後で使用される場合は、補足的な使用で理由・根拠の副詞節を導く接続詞としての働きをする 例: You should be in a hurry, for you have only 5 minutes left. 「急がなきゃだめだよ。ほんの5分しか残っていないのだから」
☆ ② The 比較級・・, the 比較級・・の構文で「・・すればするほど、それだけいっそう・・・する」の意を表す. この構文の理解には、1994年に初版発行“英文読解の透視図”(篠田重晃・玉置全人・中尾悟共著)に素晴らしい解説文があるので、以下P217~218の一部を引用させて頂く. 「この構文に登場する2つの the は定冠詞でなく、前者の the は「...すればするほど」の意で、①比較級を修飾する副詞の働きと、②副詞節をまとめ上げる接続詞の働きをもち、 ③後者の the は「それだけますます~」の意を表す程度の副詞の働きを持つ」 非常に素晴らしい解釈である.
☆ ④ 文頭の their は何を指しているのか. 文脈上、their は causes を表していると解する. これまでの既述内容より、event は 結果・effect と同義であり「ある出来事・結果」と両方の言葉を交互に置き換えながら読んでも内容の趣旨は変わらない. 英文を読んでいて未知の単語に出くわしても、多くの場合はその未知の単語と同義の単語がそれよりも前の部分に既に出ていることが多い. forces and circumstances をそのまま訳してしまうと日本語らしくなくなるので「周辺圧力」とした. , since the greater the magnitude of any event, the wider the range of forces and circumstances that affect it. では、コンマ + since で始まる副詞節では、上述②文と同じく、the 比較級・・、the 比較級・・の比較構文が使用されている.
☆ ⑨ in which we may easily get lost の which は関係代名詞で先行詞は a broad and complex field of inquiry、前の in は関係詞の前に置かれた形のもの(we may easily get lost in a broad and complex field of inquiry). このような場合の関係詞節の始まりは、in which からとなる. Ex.: This is the house which he lives in. = This is the house in which he lives in. この2つの例文では、1つ目の文では関係詞節(形容詞節でもあり、また従属節との表現もある)は which から始まる一方、2つ目の文では、in which からが関係詞節の始まりである. つまり、前置詞 in は関係詞節の一部なのである.
☆ ⑩ A great many assumptions have to be made about things that did not actually happen but seemed possible, and that, therefore, cannot be left out of account. の文末にある cannot be left out of account の主語は文頭の A great many assumptions・・の節は受動態になっている. 能動態で書き直せるとすれば、We cannot leave (V) a (the) great many assumptions (O) out of account (C). のように SVOC の第5形式の形を取ることに要注意. out of ~ は前置詞句で、基本的には「~から離れて、~の外へ、~を超えて、~を失って」などの状態を意味する場合が多い. 英語の account は、私たちが知っている、銀行の口座、勘定などの意味の他に、「考慮・配慮・根拠、重要性・重大さ」の意を表すことがあり、重要単語として認識しておこう.例1: That is out of the question. 「それは論外だ。」の意を表す. 例2: We are out of money. 「僕たちは無一文になった。」例3: The situation put him out of work. 「そのような状況で彼は仕事を失った。」that は主格の関係代名詞で先行詞は things. 文末の cannot be left out of account の主語も that になる.
Critical Analysis 4. 訳文
第1パラグラフ
① そのような場合であれば(前述からの内容を受けて)、批判的分析と証明を行う仕事はあまり困難ではない. 更に、最も目先の目標と結果とういう極狭い限られた範囲で行われる場合猶更のことである。
② 研究関連以外の世上の事から身を離し、上述の限定的条件の下で研究を行うのであれば、批判分析は恣意的なものになるだろう。
③ しかし、戦争に於いては、世上の普通の暮らしでも一般的にはそうではあるが、1つの戦役全体を構成する全ての事柄は絡まりあって繋がっており、その為、生ずる結果は、その原因が例えどんなに小さなものであっても、連続して起こる軍事行動に影響を与え、例え僅かながらにせよ、ある程度は最終的結果に修正を余儀なくさせることになる。
④ 同様に、あらゆる手段が究極的な目的にさえも影響を及ぼすのである。
⑤ 1つの原因に起因する結果については、原因と結果が明白であるにしても、そうする価値がある限り、それらを研究し続け、原因と結果の連関の詳細を紐解くことが出来る。
⑥ 同様に、手段も検討されるのだが、単に目の前の目的の為だけに評価査定されるのではなく、その目的そのものが次のそして最も究極目的達成の手段として検討されねばならない。 このように、批判分析を通して、一連の目的の流れを(1つの戦役における勝利から究極目的である講和条約に至るまで)追い求め、最終的にはもはや手段の正当性をも必要としない目的に達するのである。と言うのも、その目的の必要性が議論や検討の余地を挟まないほど明らかであるからである。
⑦ 多くの場合、特に大きくそして決定的な行動が伴う場合においては、分析は究極目的にまで至らなくてはならない、つまり、それは講和をもたらすことである。
⑧ この目的が高次元に昇華していく過程が判断の為の新しい土台を示すのである。
⑨ ある視点から見る場合に正しいと思われる手段も、高次の次元から見る場合は異なって見てとれる。
第2パラグラフ
① 批判的分析を行う場合、現象を引き起こした原因の探求と目的に即した手段を究明は常に連携してなされる。何故なら、原因究明を行うことによってのみ、検討されるべき課題が明らかにされるからである。
② 原因と結果を追い求めて、時には上へ、時には下へと行き来する一連の研究作業にはかなりの困難が伴う。
③ 結果と原因がかけ離れていればいるほど、それだけ一層、ますます同時に多くの他の諸々の原因も考慮されねばならなくなる。
④ 諸原因が結果に 及ぼし得る影響は 確定され、考慮されなくてはならない 。 何故なら、出来事の規模が大きくなればなるほど、それだけ一層出来事に影響を及ぼす周辺圧力の範囲も拡大していくからである 。
⑤ 特定の戦役での敗戦原因が明らかにされた場合、戦争全体から見た場合の幾つかの原因を知り得ることは出来る、しかしそれは全体から見れば単に1戦役における敗戦の幾つかの原因という程度に留まる、というのも、戦争の最終的結果は他の要因によっても影響を受けるからである。
⑥ 手段の分析に於いても、我々の視点がより幅広いものになるにつれ、つまり、批判する立場が高くなるにつれ、手段の検討も多種多様になっていく。
⑦ (目的と手段の関係の中に於いても)目的が高次元のものになればなるほど、それら目的を達成する為に、取るべく手段の数も増えていく。
⑧ 戦争の究極的目的は戦争に従事している全軍により同時に追求され、従って、批判分析は全ての起こった事、或いは実際には起こらなったものの起こり得た事については全て熟慮する必要がある。
⑨ そこで我々が気を付けるべきは以下のことである。このように熟慮することが時としては広範囲に亘り複雑な探求の分野に足を踏み入れてそれにより自身がとるべき本筋を間違えるかもしれない、ということである。
⑩ そこで、実際には生じなかったものの、起こる可能性があった事、従って考慮しないわけにはいかない事柄について、予め多くの推定をしておかなくてはならない。