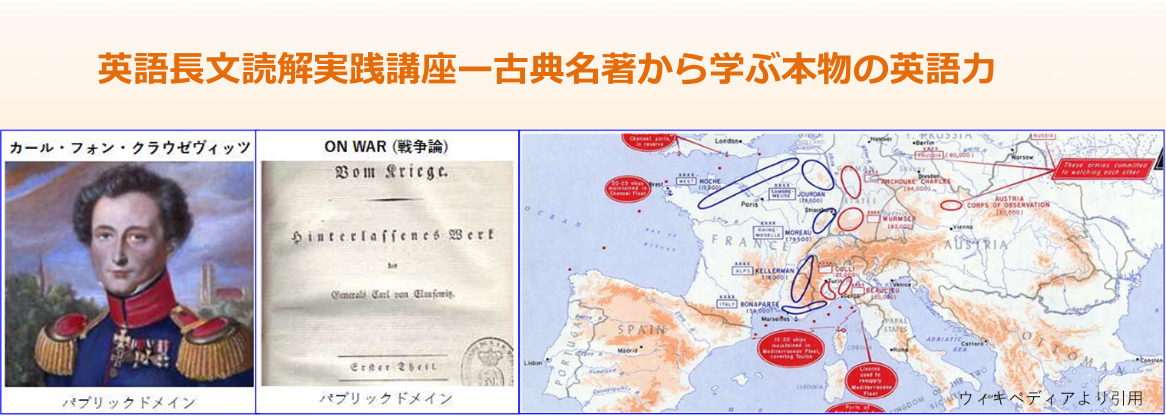Critical Analysis 7. 原文
We must now break off this discussion. It will suffice to show the comprehensive, intricate and difficult character which a critical analysis may assume if it extends to ultimate objectives-in other words, if it deals with the great and decisive measures which must necessarily lead up to them. It follows that in addition to theoretical insight into the subject, natural talent will greatly enhance the value of critical analysis: for it will primarily depend on such talent to illuminate the connections which link things together and to determine which among the countless concatenations of events are the essential ones.
But talent will be needed in another way as well. Critical analysis is not just an evaluation of the means actually employed, but of all possible means-which first have to be formulated, that is, invented. One can, after all, not condemn a method without being able to suggest a better alternative. No matter how small the range of possible combinations may be in most cases, it cannot be denied that listing those that have not been used is not a mere analysis of existing things but an achievement that cannot be performed to order since it depends on the creativity of the intellect. We are far from suggesting that the realm of true genius is to be found in cases where a handful of simple, practical schemes account for everything. In our view it is quite absurd, though it is often done, to treat the turning of a position as an invention of great genius. And yet such individual creative evaluations are necessary, and they significantly influence the value of critical analysis.<
When on 30 July 1796, Bonaparte decided to raise the siege of Mantua in order to meet Wurmser’s advance, and fell with his entire strength on each of the latter’s columns separately while they were divided by Lake Garda and the Mincio, he did so because this seemed the surest way to decisive victories. These victories in fact did occur, and were repeated even more decisively in the same way against later attempts to relieve Mantua. There is only one opinion about this: unbounded admiration.
And yet, Bonaparte could not choose this course on 30 July without renouncing all hope of taking the city; for it was impossible to save the siege train, and it could not be replaced during the current campaign. In point of fact, the siege turned into a mere blockade and the city, which would have fallen within a week if the siege had been maintained, held out for six more months despite all Bonaparte's victories in the field.
第1パラグラフ
※語・句注釈
*① break off (句動詞) = 「打ち切る、解消する」 *② intricate (形容詞) = 「複雑な、入り組んだ」 *③ it follows that ~ (慣用表現) = 「~ということになる」 *③ in addition to ~ (前置詞句) = 「~に加えて」 :③ natural talent (名詞句) = 「天賦の才能」 *③ countless (形容詞) = 「数えきれない程の、無数の」 *③ illuminate (動詞) = 「解明する、啓蒙する、照らす」 *④ as well (副詞句) = 「~もまた、同様に」 *⑤ formulate (動詞) = 「 *⑥ concatenations (名詞) = 「繋がり、一連、連結」 *⑥ after all (前置詞) = 「結局」 *⑨ a handful of ~ (前置詞句) = 「一握りの~」
第2パラグラフ
※語・句注釈
*① siege (名詞) = 「要塞・砦などの包囲攻撃」raise the siege of ~「~の包囲を解く」 *① Mantua (固有名詞) = 「マントヴァ、イタリア北部ロンバルディア州にある都市」 *① meet (動詞) = 軍事関連での使用では「立ち向かう、戦う」の意を表す *① columns (名詞) = 軍事用語として船体の縦列を示すが、ここでは「ガルダ湖とミンチョ川に陣取っているオーストリア軍が次々と」を意味する *① Wurmser (固有名詞) = 「オーストリアの伯爵・軍人、ヴルムザー将軍:1724-1797」 *① fall on (熟語動詞) = 「敵に襲い掛かる(attack)」 *① Lake Garda (固有名詞) = 「北イタリアにあるイタリア最大の湖」 *① Mincio (固有名詞) = 「ガルダ湖を経由して流れるイタリア北部のミンチョ川」 *③ unbounded (形容詞) = 「無数の、限りない、際限のない、抑えの効かない」 *③ And yet (2語で接続詞の働き) = 「それにも関わらず、でも、だが」前後の文脈が異なる時などに使われる *④ train (名詞) = 軍事用語で「兵站或いは輜重(しちょう)・現在で言う軍需物資輸送隊」に充たる *⑤ in point of fact (前置詞句→ここでは副詞句) = 「実際のところ、実質上」 *⑤ blockade (名詞) = 「封鎖、封鎖部隊」 *⑤ hold out (熟語) = 「持ち堪える、抗う(抵抗する)、提供する」

Critical Analysis 7. 解説
第1パラグラフ
① We must now break off this discussion. ② It will suffice to show the comprehensive, intricate and difficult character which a critical analysis may assume if it extends to ultimate objectives-in other words, if it deals with the great and decisive measures which must necessarily lead up to them. ③ It follows that in addition to theoretical insight into the subject, natural talent will greatly enhance the value of critical analysis: for it will primarily depend on such talent to illuminate the connections which link things together and to determine which among the countless concatenations of events are the essential ones.
④ But talent will be needed in another way as well. ⑤ Critical analysis is not just an evaluation of the means actually employed, but of all possible means-which first have to be formulated, that is, invented. ⑥ One can, after all, not condemn a method without being able to suggest a better alternative. ⑦ No matter how small the range of possible combinations may be in most cases, it cannot be denied that listing those that have not been used is not a mere analysis of existing things but an achievement that cannot be performed to order since it depends on the creativity of the intellect. ⑧ We are far from suggesting that the realm of true genius is to be found in cases where a handful of simple, practical schemes account for everything. ⑨ In our view it is quite absurd, though it is often done, to treat the turning of a position as an invention of great genius. ⑩ And yet such individual creative evaluations are necessary, and they significantly influence the value of critical analysis.
☆ ② It will suffice to V・・で、it は to 不定詞以下を受ける形式主語、「~することで十分だろう」の意を表す. if 節以降は条件節なので、文頭のは具体例も挙げ長くなっているので文末に回されていると考える. It will suffice to・・・は to 不定詞の it の形式主語構文で帰結節との認識で読んでいく. if 節の it は文脈より a critical analysis を示す. If it extends・・・で示したものをダッシュ(-)で繋いで、in other words からも分かるように、更に具体的にその内容を表現している. 「批判分析が究極的目的にまで広がる場合、つまり、換言すると、当然究極的目的に至る重要且つ決定的な手段を扱う場合には」と言い換えられている.
☆ ③ it follows that ~ は it を形式主語構文での慣用表現で「~ということになる」の意を表す. 従属接続詞 that の中で書かれている内容は全て that 内で完結される. in addition to theoretical insight into the subject, natural talent will greatly enhance the value of critical analysis の内容は、コロンを使用して具体的に後に理由を表す接続詞の for に依って表されいる. ここでは、to 不定詞の形式主語構文が使われており、it は2つの to 不定詞の内容を受けていることを確認すること. to illuminate・・・と to determine・・・である.
☆ ⑤ but of all possible means-which first have to be formulated, that is, invented. のダッシュ(-)は前の名詞句 all possible means を具体的に説明していると同時に、which は継続用法で同じくこの名詞句の補足説明をしており、ある意味、強調する為の表現になっていると考える.
☆ ⑦ No matter 疑問詞 (who, what, how, where 等)の並びで「たとえ~にせよ」と譲歩の接続詞としての意を表す. これらは、複合関係副詞の whoever, whatever, however, wherever, whenever を文頭に持ってくる場合と同じ意味を持つ. 当文は、No matter how + small (形容詞) the range of possible communications may be・・ となっており、複合関係副詞を用いて同じ内容を表す場合は、However small the range of possible communications may be・・ となる. 因みに、文頭に複合関係副詞が来る場合、however に限って2つの形態をとる事が出来る. 1) However + 形容詞 + S + V の形、Ex.1: However clever he is, he can’t get out of the trap. 「どんなに彼が賢かろうが、その罠から抜け出すことは出来ない。」 2) However + S + V の形、Ex.2: However you try it, the result is the same. 「君がどのようにそれにトライしても、結果は同じだよ。」 当文の解釈は非常に難しい内容といえよう. 但し、このような難しい表現の場合は、記述内容の逆手を取ってそれを訳として理解に努めるのも1つの手である. it cannot be denied that listing those that have not been used is not a mere analysis of existing things but an achievement that cannot be performed to order since it depends on the creativity of the intellect. It cannot be denied that・・・は形式主語構文の it で that 以下全体を受ける. この文に限らずに、(既出ではあるが) 従属接続詞の that で重要なことは、that 節以下の修飾要素・副詞句 (前置詞句等) は必ず that 内のみで働くということである. つまり、listing those that have not been used is not a mere analysis of existing things but an achievement that cannot be performed to order since it depends on the creativity of the intellect. で述べられている事柄は、否定し得ない、ということである. 既述内容を見ていくと、an achievement that cannot be performed to order は字ずらだけを見ると「強制によっては実行されない偉業」となるが、いまいち訳としてピンとこないので、逆転の発想で、:強制によっては実行され得ない偉業:というのなら、「自発的創造性を以てすれば成し得る」と逆から考えることが出来るはず.
☆ ⑨ we are far from suggesting that・・・は直訳すれば「・・・を主張しているのからはかなり離れている」となるが、読み取りにくくなるので「・・・しているわけではない」と訳している. 読解すべき内容は、we can’t suggest・・と同じである.
☆ ⑩ 文頭の And yet は、既出の事柄に対しての逆説的な表現で前文と繋げる働きをて、「それでもなお」の意を表す.>
第2パラグラフ
① When on 30 July 1796, Bonaparte decided to raise the siege of Mantua in order to meet Wurmser’s advance, and fell with his entire strength on each of the latter’s columns separately while they were divided by Lake Garda and the Mincio, he did so because this seemed the surest way to decisive victories. ② These victories in fact did occur, and were repeated even more decisively in the same way against later attempts to relieve Mantua. ③ There is only one opinion about this: unbounded admiration.
④ And yet, Bonaparte could not choose this course on 30 July without renouncing all hope of taking the city; for it was impossible to save the siege train, and it could not be replaced during the current campaign. ⑤ In point of fact, the siege turned into a mere blockade and the city, which would have fallen within a week if the siege had been maintained, held out for six more months despite all Bonaparte’s victories in the field
☆ ① ナポレオンが決心したのは to raise the siege of Mantua in order to meet Wurmser’s advance 「ヴルムザー将軍を迎え撃つ為にマントヴァ包囲攻勢を解いたこと」であり、時間軸のながれで、その後に「彼は全軍の力を結集して戦った」のである. それが、Wurmser’s advance の後のコンマが置かれて、等位接続詞の and で 次の行動を示す fell (with his entire strength) on・・・で示されている. 決して「全軍の力を結集して・・・戦うことを決心した」訳ではないことに注意. 戦うことも決心したことに含めるのであれば、Wurmser’s advance and fall with his entire strength on・・・と、Wurmser’s advance の後にコンマは置かず、しかも等位接続詞で結ばれる動詞は現在形の fall になっているはずだから.
☆② These victories in fact did occur では、実際に occur したことを強調するために、助動詞の did を本動詞 occur の前に置いている.
☆⑤ which は非制限(継続)用法の関係代名詞. この which は継続用法の主格の関係代名詞であると同時に仮定法過去完了の帰結節を成している.
~重要文法事項~
It is ~ that・・・の形式主語構文・強調構文のまとめ
強調構文とは、it is ~ that・・・、it is ~ which・・・の形で、~の部分を強調する場合に使用するものである. 他方で、it is ~ that 構文には、it を形式主語として that 以下を受ける形式主語構文(~の部分が形容詞或いは名詞になる)もあるが、文脈から区別できる場合、形から区別出来る場合も多くあり、以下に形式主語なのか強調構文なのかの識別について記す.Ex.1: It is the decision of the board of directors that all the employees must come to work on time.Ex.2: It is the decision of the board of directors that all the employees are angry with.上記2つの英文は、形としてはどちらも it is ~ that・・・構文といえる.
Ex.1は、「全ての従業員は定刻に出社しなくてはならないのは、取締役会の決定事項です。」
It は形式主語で that 以下を受け、that 節は名詞節となる.
Ex.2は、「全ての従業員が怒っているのが取締役会の決定事項である。」の意を表し、 with の目的語が the decision of the board of directors で、この名詞句が強調された強調構文である. 強調構文では、強調したい語・句・節を it is と that の間に挟んで強調する. 形式主語構文と強調構文の識別は重要で、文法がしっかりと身についていないと無理強いな訳をしてしまい、そうなると読解どころではなくなってくる.
☆ 識別のポイント1. (it is ~ that・・・で、~ の部分が名詞要素の場合)
It is ~ that・・・で ~ の部分が名詞要素の場合、強調構文であれば ~ の部分は that 以下で必ず主語(主部)か述語(述部)になっている. that 以下がそれだけで文として成立する場合は形式主語構文である. 上で2)を見てきたので繰り返しになるが、that 以下は all the employees are angry with. でこれでは文として成立しない. 前置詞 with の目的語がないからである.
☆ 識別のポイント2.
強調構文で強調されるのは、必ず①名詞要素か②副詞要素であるということ. It is pp(過去分詞) that・・・やIt is 形容詞 that・・・の場合は必ず形式主語構文であるということ.
☆ 識別のポイント3. (it is ~ that・・・で、~ の部分が副詞要素の場合)
It is ~ that・・・で、~ の部分が副詞要素の場合は必ず強調構文になる.Ex.1: It was last Saturday that she was elected Prime Minister. ~ の部分が副詞句の on Saturday であるが、副詞要素が強調される時のポイントは、it is と that を文から外しても残りの部分で文として成立することである. ここで、it is と that を外してみると、last Saturday she was elected Prime Minister. となり、文として成立する. 通常であれば、She was elected Prime Minister last Saturday. となる場合が多いと思うが、Last Saturday, she was elected Prime Minister. としても意味は通じるし、最初に Last Saturday がきているとすると、Last Saturday が何かしらの要因で強調されていると考えて良い.Ex.2: It was only after they went to the office that they realized that all the papers related to the contract had gone. 副詞節の only after they went to the office が it is と that の間に挟まれている形であるが、これも it is と that を省いてやると、only after they went to the office, they realized that all the documents related to the contract had gone. となり副詞節を含む文として成立する. つまり、it is ~ that・・・で ~ の部分に副詞・副詞句・副詞節が来る場合は必ず強調構文になる.
Critical Analysis 7. 訳文
第1パラグラフ
① 私たちはこの議論をここで打ち切らなくてはならない。
② 批判的分析が究極的目標にまで広がる場合、つまり、換言すると、必然的に究極目標に繋がる重要且つ決定的な手段を扱う場合には、批判分析が伴う広範囲で複雑且つ多大なる困難な特徴を示すには十分だろう.
③ この考察についての理論的洞察に加えて、批判分析の価値を大いに高めるのが天賦の才能だろう。というのも、事柄の繋がりを解明して、また無数の出来事が連なる中で何が重要であるかを決定できるのは、基本的には天賦の才能にかかっているからだ。
④ しかし、またこの天賦の才能というのは他の方法でも同じく必要になる
.⑤ 批判的分析は実際に使用された手段を単に評価するだけでなく、実際には使用されなかったにせよ、取り得る可能性のあった全ての手段の評価するものであり、これら起こり得たものについては、批判分析を通して先ずは明確に示され、究極的には批評家によって発明されなければならないのである。
⑥ より優れた代替案を明示しなれば、結局はある手段を非難することなど出来はしない。
⑦ 殆どの場合に於いて、取り得る可能性のあった手段の組み合わせの範囲がどんなに小さいものにせよ、使用されなかった手段を列挙するには目の前にある既存手段の単なる分析ではなくて、それは智の創造力に依る自発的偉業なのである、ということは否定出来ない。
⑧ 真の天才の領域については、ほんの一握りの明快且つ実用的に深く練られた案が全てを説明出来る場合において発見されるべきものだ、などと我々は主張しているわけではない。
⑨ よくあることだが、我々の観点からすると、敵側面或いは後方に回り込むことが偉大なる天才の発明のごとく扱うことは極めて馬鹿げているものである。
⑩ それでもなお、このような個々の創造性を有した評価は必要であり、それこそが批判的分析の価値に影響を与えると言える。
第2パラグラフ
① 1796年6月30日、ナポレオンは、進軍して来るヴルムザー将軍率いるオーストリア軍を迎え撃つためマントヴァ要塞の包囲を解くと決断し、彼のもつ全ての力で以てして、オーストリア部隊はガルダ湖とミンチョ川に分散している中、縦列状態で向かってくるミンチョ川の各部隊を別々に撃破した際、これが決定的勝利につながる確実な方法だと思えたので、ナポレオンはそうしたのであった。
② そして、実際にナポレオンは連戦連勝し、その後のオーストリア軍によるマントヴァ要塞救援軍に対しても、同じ手段で更によりいっそう決定的に勝利を続けたのである。
③ 言えることは唯一、惜しみない賞賛のみである。
④ それにも関わらず、この戦いを続けるのであれば、ナポレオンは7月30日には、マントヴァ要塞の攻囲は放棄しなればならなかった。というのも、包囲攻撃するための兵站確保は不可能であったし、進行中の地上での戦闘の間に、新たに包囲攻撃部隊を入れ替え、配置することも出来なかったからである。
⑤ 実質上、包囲攻撃は単なる封鎖活動となってしまった。包囲攻撃が続いていたとしたら、1週間もあれば陥落しいたであろう要塞都市は、地上戦ではナポレオンの連連勝が続いていたにも関わらず6か月以上も持ち堪えたのである。