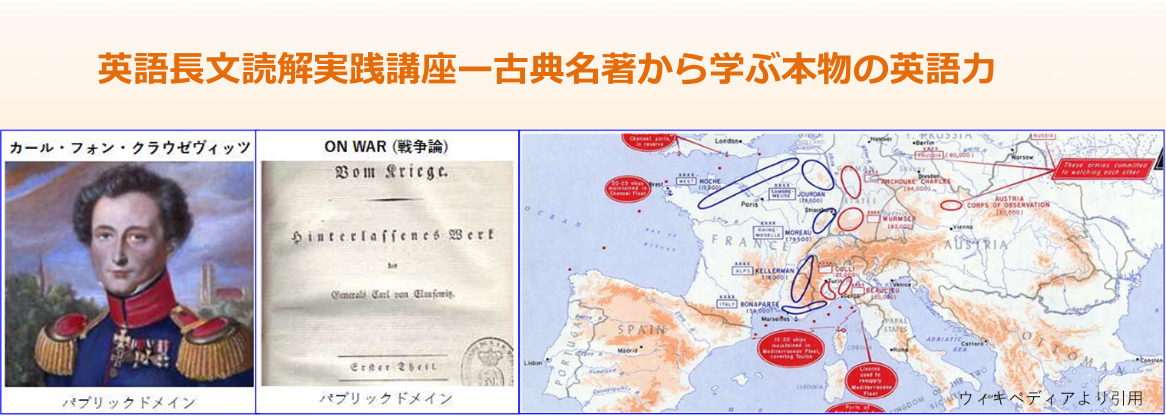Critical Analysis 3. 原文
But it would be wishful thinking to imagine that any theory could cover every abstract truth, so that all the critic had to do would be to classify the case studied under the appropriate heading. Equally, it would be ridiculous to expect criticism to reverse course whenever it came up against the limits of a sacrosanct theory. The same point of analytical investigation which creates a theory should also guide the work of the critic who both may and should often cross into the realm of theory in order to elucidate any points of especial importance.
The function of criticism would be missed entirely if criticism were to degenerate into a mechanical application of theory. All the positive results of theoretical investigation―all the principles, rules, and methods―will increasingly lack universality and absolute truth the closer they come to being positive doctrine. They are there to be used when needed, and their suitability in any given case must always be a matter of judgment. A critic should never use the results of theory as laws and standards, but only―as the soldier does―as aids to judgment. If, in tactics, it is generally agreed that in the standard line of battle cavalry should posted not in line with but behind the infantry, it would nevertheless be foolish to condemn every different deployment simply because it is different. The critic should analyze the reasons for the exception. He has no right to appeal to theoretical principles unless these reasons are inadequate.
Again, if theory lays it down that an attack with divided forces reduces the probability of success, it would be equally unreasonable, without further analysis, to attribute failure to the separation of forces whenever both occur together; or when an attack with divided forces is successful to conclude that the original theoretical assertion was incorrect. The inquiring nature of criticism can permit neither. In short, criticism largely depends on the results of the theorist’s analytic studies. What theory has already established the critic need not go over again, and it is the theorist’s function to provide the critic with these findings.
The critic’s task of investigating the relation of cause and effect and the appropriateness of means to ends will be easy when cause and effect, means and ends, are closely linked. When a surprise attack renders an army incapable of employing its powers in an orderly and rational manner, the effect of the surprise can not be questioned. When theory has established that an enveloping attack leads to greater, if less certain, success, we have to ask whether the general who used this envelopment was primarily concerned with the magnitude of success. If so, he chose the right way to go about it. but he used it in order to make more certain of success, basing his action not so much on individual circumstances as on the general nature of enveloping attacks, as has happened innumerable times, then he misunderstood the nature of the means he chose and committed an error.
第1パラグラフ
※語・句注釈
*① wishful thinking (名詞句) = 「希望的観測」 *① abstract (形容詞) = 「抽象的な」 *② sacrosanct (形容詞) = 「極めて神聖で侵す事の出来ない」 *③ elucidate (動詞) = 「明らかにする、解明する」 *④ degenerate (自動詞) = 「悪化する・退化する・堕落する」 *⑤ absolute (形容詞) = 「絶対の、完全な、疑う余地のない、専制の、独断的な」 *⑥ suitability (名詞) = 「適格性、適合性」 *⑧ cavalry (名詞) = 「騎兵隊、現在では装甲機動部隊やヘリ機動部隊を指す」 *⑪ lay down (熟語動詞) = 「規定する、定める」 *⑭ provide (動詞) = 「provide A with B で、AにBを提供する・用意する」
第2パラグラフ
※語・句注釈
*① cause and effect (名詞句) = 「原因と結果」 *② render (動詞) = SVOC の形で「~にする・させる」ここでは make と同義語. *③ if less certain (even if it is less certain) は挿入句(挿入節)) = 「(たとえ、確かさは劣るにせよ」 *③ enveloping attack (名詞句) = 「包囲攻撃」 *③ magnitude (名詞) = 「規模・巨大さ・重要性」 *④ go about (句動詞) = 「取り組む、やってみる」 *④ innumerable (形容詞) = 「多くの、数えきれない」
.
Critical Analysis 3. 解説
第1パラグラフ
① But it would be wishful thinking to imagine that any theory could cover every abstract truth, so that all the critic had to do would be to classify the case studied under the appropriate heading. ② Equally, it would be ridiculous to expect criticism to reverse course whenever it came up against the limits of a sacrosanct theory. ③ The same spirit of analytical investigation which creates a theory should also guide the work of the critic who both may and should often cross into the realm of theory in order to elucidate any points of special importance.
④ The function of criticism would be missed entirely if criticism were to degenerate into a mechanical application of theory. ⑤ All the positive results of theoretical investigation―all the principles, rules, and methods―will increasingly lack universality and absolute truth the closer they come to positive doctrine. ⑥ They are there to be used when needed, and their suitability in any given case must always be a matter of judgment. ⑦ A critic should never use the results of theory as laws and standards, but only―as the soldier does―as aids to judgment. ⑧ If, in tactics, it is generally agreed that in the standard line of battle cavalry should be posted not in line with but behind the infantry, it would nevertheless be foolish to condemn every different deployment simply because it is different. ⑨ The critic should analyze the reasons for the exception. ⑩ He has no right to appeal to theoretical principles unless these reasons are inadequate.
⑪ Again, if theory lays it down that an attack with divided forces reduces the probability of success, it would be equally unreasonable, without further analysis, to attribute failure to the separation of forces whenever both occur together; or when an attack with divided forces is successful to conclude that the original theoretical assertion was incorrect. ⑫ The inquiring nature of criticism can permit neither. ⑬ In short, criticism largely depends on the results of the theorist’s analytic studies. ⑭ What theory has already established the critic need not go over again, and it is the theorist’s function to provide the critic with these findings.
☆ ① it would be wishful thinking to imagine that 節・・では、it は to imagine 以下を受ける形式主語の it で、would be は仮定法の婉曲表現. 通常の現在形平叙文で構成されている文体に突如として現れる助動詞の過去形には注意が必要. imagine の目的語である that 節内の , so that (コンマ + so that) は所謂 so that 構文の一種である. so that 構文といえば、① 目的 He worked so hard that his son could go to the university. 「息子が大学に通えるために彼はとてもよく働いた。」や ② 結果 He went to the station so early that he could get the first train. 「彼はとても早く駅に行ったので始発の電車に間に合った。」 或いは、③ 程度 He was so kind that everyone loved him. 「彼はとても親切だったので、誰からも好かれた。」のように、目的・結果・程度を表す用法があるが、, so that (コンマ + so that) の場合は、前節の結果を受けての結果を表す表現に使うことを覚えておきたい. critic は日本語訳では、「批判するもの、批評家、批判者」に充たるが、ここでは、ある意味、擬態化して前出の criticism として批判の総称のような理解で良いと思われる. また、any theory could cover every abstract truth をどう捉えるか? Any child could do that. 「どんな子供でもそれは出来るだろう。」(TAISHUKAN’S GENIUS English-Japanese Dictionaryより引用)という表現があり、これは仮定法婉曲表現とも結びついていて、「大変たやすいことだ」を含意していると考えられる. これらより、訳文としては、「どのような理論でもあらゆる抽象的真理を扱うことが出来るであろうから、批判は~しさえすれば良い。」としている.
☆ ② 当文も仮定法の婉曲表現. whenever it came up against the limits of a sacrosanct theory と came 過去形が使用されえているのは、当文が仮定法の用法であるため.
☆ ③ which は限定用法の関係代名詞. 関係代名詞から前へ訳し上げると日本語らしくなる.
☆ ④ 仮定法は、著者或いは話者自身が実際に起こりえる可能性が低いと認識している事を if 節で条件設定して、帰結節では、起こりえる可能性が低い条件に基づいて想定を述べるものである. 端的に言えば、非現実なことを条件設定し、その非現実の条件に沿った非現実の想定を述べるものである. 現実と非現実の差が時制の差になって現れると考えれば良い. 現在に於いての非現実の仮定では動詞の過去形を用い、過去に於いての仮定であれば動詞の過去完了形を用いる. 当文では、if S were・・となっているが、これは if S should 動詞…、若しくは Should it 動詞…と倒置形で表しても良いが、意味としては「万が一~~するようなことがあれば」と、強い意味合いで未来に対する非現実の条件設定を表すことも出来る. 帰結となる The function of criticism would be missed entirely と completely と同義である entirely がつかわれていることからも強意であるのが読み取れる.
☆ ⑤ All the positive results of theoretical investigation―all the principles, rules, and methods―will increasingly lack・・・での―(ダッシュ)のあとで、all the principles of theoretical investigation の詳細説明或いは補足説明をするために使用されている.
☆ ⑦ A critic should never use the results of theory as laws and standards, but only―as the soldier does―as aids to judgment. は、S should never use A as A’ but as B. と理解して、-as the soldier does-は挿入節で、 「批判は理論の成果を法則や規範として使用するべきではなく、-実際の戦場で戦っている兵士たちはそうするのであるが―判断の為の一助として使うべきである」との意を表しているのである.
☆ ⑧ 当文の if 節は、 If, in tactics, it is generally agreed that・・・と直説法での表現で、帰結節は、it would nevertheless・・・・ because it is different. と仮定法の婉曲表現が使われている. 文脈より文頭の if は いわゆる仮定法でよく使われる「もし、」意味を表している訳ではなく、加えて動詞が現在形であることから当該条件節の個所では事実に反する事柄を述べているのではなく、戦術上は当然と見なされている事象を譲歩の意味合いで「たとえ、~~であるにしても」との内容を述べているのである. それに対して帰結節では、直説法で断定的に述べるのを避けて一歩控えめな表現として助動詞の過去形を使用して婉曲表現を取っているのである. 尚、cavalry は乗馬して戦う兵士(部隊)を表し、現代の戦争では機動力に富む装甲車群やヘリ群に相当するものである.
☆ ⑪ Again, if theory lays it down that an attack with divided forces reduces the probability of success, it would be equally unreasonable, without further analysis, to attribute failure to the separation of forces whenever both occur together; or when an attack with divided forces is successful to conclude that the original theoretical assertion was incorrect.当文でもまた if 節で動詞の現在形が使用される条件設定で文自体が長く、またセミコロンで継続されて難解に見えるものの、文頭に again とあるように、これまで読んできた内容の繰り返しであろうことが想像できる. If 節を使用した現在形動詞の条件節であるので、事実に反することを条件設定している訳ではない、ことを先ず理解すること. 次に、やはり上述の文のように帰結節は it would・・・と仮定法の婉曲表現であることが前文で出てきた形であることを理解する. 文頭部の if は⑧文目と同じように、「もし~ならば」というよりも意味場としては even if に近い「たとえ、~ であるにしても」と解釈するほうがスムースに文意を取りことが出来る.
☆ ⑫ The inquiring nature of criticism can permit neither. では、neither が permit の目的語でここでは代名詞としての使用である. 本来で」あれば、neither of them と記したほうが分かりやすいだろう. neither によって「どちらも~でない」意を表すので、them は前文の2つの言い分若しくは見解のことである. The inquiring nature of の nature はここでは、spirit と同義語と捉える.
☆ ⑭ 文頭のwhat は先行詞を含む関係代名詞. 名詞節 + 名詞 + 動詞・・・の形をどう読み解くか?go over 目的語 で「入念に調べる、綿密に調べる」ということが分かれば、what theory has already established the critic need not go over では、前置詞の over の目的語がないことから目的語が欠けていることを確認. what を theory に掛かる関係形容詞として取り、established の目的語を the critic として読もうとすれば、need not go over をそう理解するか説明が出来ない. そこで、先の説明の前置詞 over の目的語がないことから、what theory has already established の個所は what は先行詞を含む関係代名詞であることから、theory を主語と取り、「理論が既に確立したこと」を表す名詞節と取り、この名詞節が go over の 前置詞 over の目的語と理解すれば、ここは強調の為の倒置が行われていると考え、the critic need not go over again what theory has already established とすれば「批判は理論が既に確立したものを再度調査する必要はない」と意味がすんなり通る.
第2パラグラフ
① The critic’s task of investigating the relation of cause and effect and the appropriateness of means to ends will be easy when cause and effect, means and ends, are closely linked. ② When a surprise attack renders an army incapable of employing its powers in an orderly and rational manner, the effect of the surprise can not be questioned. ③ When theory has established that an enveloping attack leads to greater, if less certain, success, we have to ask whether the general who used this envelopment was primarily concerned with the magnitude of success. ④ If so, he chose the right way to go about it. ⑤ But if he used it in order to make more certain of success, basing his action not so much on individual circumstances as on the general nature of enveloping attacks, as has happened innumerable times, then he misunderstood the nature of the means he chose and committed an error.
☆ ② render は make と同じ使役動詞の用法なので、a surprise attack (S) renders (V) an army (O) incapable (C) と第5形式の文を作る.
☆ ③ if less certain は挿入句で、「確からしさは少なくなるにせよ」つまり「確率は劣るにせよ」の意味になる. コンマ, even if it is less certain, (コンマ) になっていれば挿入節. このような場合の挿入句、挿入節は「~だけれども、例え~であるにしても」などの譲歩の意を表す場合が多い. 勿論、判断の決め手となるのは文脈であり、同じ挿入句でも名詞に対する修飾句であったり、同義語であったりする場合があることも要注意.
☆ ⑤ basing his action・・・以下は分詞構文. as has happened innumerable times (数えきれない程何度も起きていることではあるが), は挿入節で、この as は疑似関係代名詞で前にも見たように前節全体を受けている(Critical Analysis 1 第2パラグラフ②文目の as is so often done と同じ).
~重要文法事項~
助動詞の過去形について
助動詞は、その文字通りに“動詞を助ける”意味合いがあり、例えば、will, can, may, should, must, shall などが主なものとして思いつくだろう. これら助動詞は全て本動詞の前に置かれ、例えば、Ex.1: He will go to the front line in the battle in a week. 「彼は1週間以内には戦場の最前線に向かうことになろう 若しくは、彼は1週間以内には戦場の最前線に向かうことに決めている.」などの意味になるだろう. ここは、前後脈略そしてこの話者の心情によって変わって来よう. 例えば、Ex.2: I will go the battle place next week. なれば、「俺は来週には戦場に行ってくる(んだ).」という理解しかない. ここでの 助動詞 will は強固な意志を表す解釈になる. 上記2つの例文を見てわかるように、話者の視点からによっては解釈の仕方に若干のニュアンスの違いの可能性は残るが、助動詞の本質は話者・書き手の“心情・気持ち”を示している、いうことである. 助動詞のポイントとしては、ここにあると言っても過言ではなく、この点をしっかりと押さえて頂きたい. 他の can, may, should, must 等についても同じである. 英文を読んでいると、これまで通常の現在形の動詞で書かれている中で、突如として助動詞の過去形で記述されている個所などに遭遇することもあり、よくあるものに、would (will の過去形) がある. そのような場合の助動詞の過去形には注意が必要だ. 助動詞の過去形を使用する際は、話者・書き手の“心情・気持ちの在りよう”の度合いが更に大きいことを意味する. 勿論、前後脈略の上で只単に時制に合わせて使われている場合もあるが、ここで言っているのは、これまで通常の現在形で書かれていた文態の中に突如として、助動詞の過去形が出てくる場合の時だ. 本章、Critical Analysis 3. では、最初の書き出しから、But it would be wishful thinking to imagine that・・・の表現で始まっている. 当文は、it と to 不定詞の形式主語構文の1つである. 厳密に言えば、仮定法の婉曲表現で、to imagine that 以下が仮定の条件節と同じ働きをして、it would be wishful thinking で to imagine 以下の仮定の条件に基づいた作者の想定が主張されている帰結節なのである. 仮定法の詳細については、Critical Analysis 6. の解説最後の ~重要文法事項~ を参照頂きたい.
Critical Analysis 3. 訳文
第1パラグラフ
① 理論はあらゆる抽象的真理を取り扱えるだろうから、批判は適宜な課題の下で研究されている個別事例を理論に沿って振り分けさえすれば良いのだと考えるのは、希望的観測というものであろう。
② また同じように、批判が神聖な理論の境界に足を踏み入れそうになると、批判は直ちに180度方向転回すると考えるのも一笑に付されるものであろう。
③ 理論を造り上げるのは分析的研究の精神であるが、その同じ精神が批判の仕事を導くため批判が理論の領域に入り込むかもしれないし、そこでは批判は、批判にとって特別に重要になると考えられる点を明らかにする為に、理論の領域に足を踏み入れても良いし、またそうしなくてはならないのである。
④ 批判が理論を単に機械的に運用することに成り下がってしまうのであれば、批判の機能は完全に失われてしまうだろう。
⑤ 理論的研究の全ての積極的な成果-全ての原則・規則そして規律―は、それらが積極的な教義的解釈になればなるほど、普遍性と絶対的真理性を失っていくことになろう。
⑥ これらは必要に応じて使われるものであり、その適格性については常に使用する者の判断に委ねられるのである。
⑦ 批判は、理論のこれらの成果を決して法則・基準として使うべきではなく、実際の戦場で戦っている兵士たちが臨機応変に対応せざるを得ないように、判断のための材料として扱うべきである。
⑧ 例え、戦術上、標準的な騎兵(隊)の序列は歩兵(部隊)と同列ではなく、歩兵の後方に配置されることが一般的認識であるにせよ、にも関わらず、単に序列が異なるというだけでその采配を非難するのは馬鹿げているであろう。
⑨ 批判は例外がその例外たるべき根拠を分析しなくてはならない。
⑩ 根拠が不十分な場合に、批判は理論的原理に判断を求めて批判を行うのである。
⑪ 戦力を分散した攻撃が成功の確立を下げると理論によって決まっているとしても、攻撃の成功率が下がるのと戦力の分散による失敗が一緒に起きるときは常に、詳細の分析をすることもせずに、戦力の分散が原因であるとしたり、或いは戦力を分散した攻撃が成功したからと言って先の理論が正しくないとする言い分は受け入れられないだろう。
⑫ 批判の探求精神はどちらの言い分も許容出来はしない。
⑬ 要するに、批判を支えるのは、理論の分析的研究の成果なのである。
⑭ 批判は理論に依って既に確立されていることについては今更確認する必要はないし、理論の役割とはその確率されたものを批判が使えるようにすることなのである。
第2パラグラフ
① 戦争の因果関係と目的に対する手段の使用が適切であったかどうかを研究するのが批判の本務だが、原因と結果、手段と目的それぞれが接近していれば、容易だろう。
② 奇襲攻撃を受けたがために秩序正しく合理的に戦闘力を十分に発揮出来ない状況にされたら、奇襲の効果は疑いようのない。
③ 包囲攻撃は、確率的にはそうでもないが、より大きな勝利を導くというのが理論で確立されている際に、我々が問わなくてはならないのは、この包囲攻撃を指揮した将帥の主たる想定・計画が勝利の大きさであったかどうかである。④ もし、そうであるなら、その将帥は正しい選択をしたことになる。
⑤ だが、もし彼が勝率の高さを狙って、個々の諸状況に基づかず、包囲攻撃の一般的性質 に基づいて包囲攻撃を実施したとなれば、これは歴史上幾度なく繰り返されたことであるが、彼は選んだ手段の性質を見誤ったことになるし、過ちを犯したことになる。